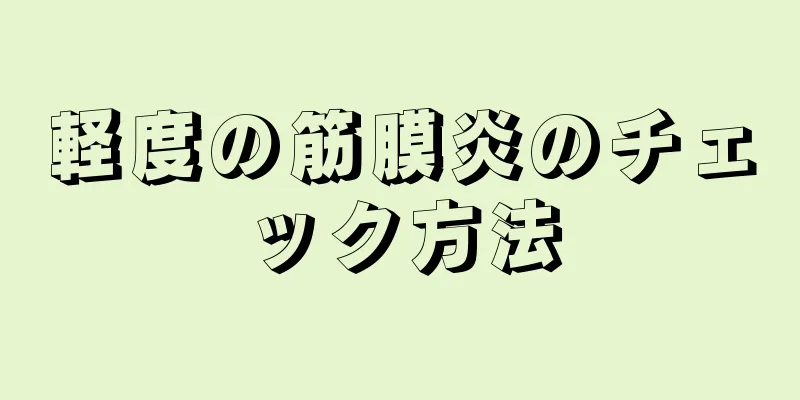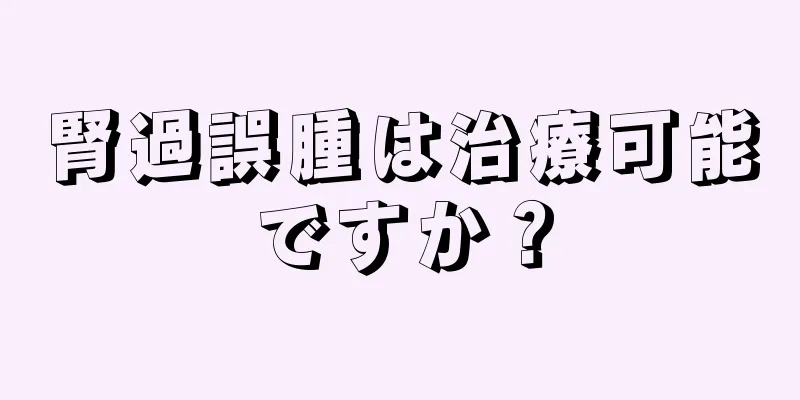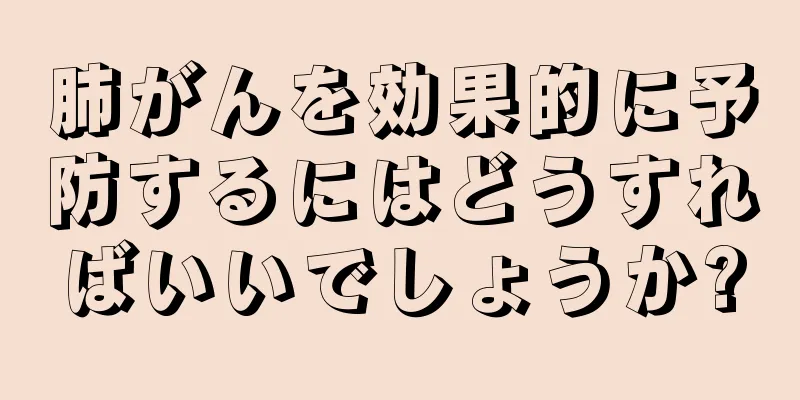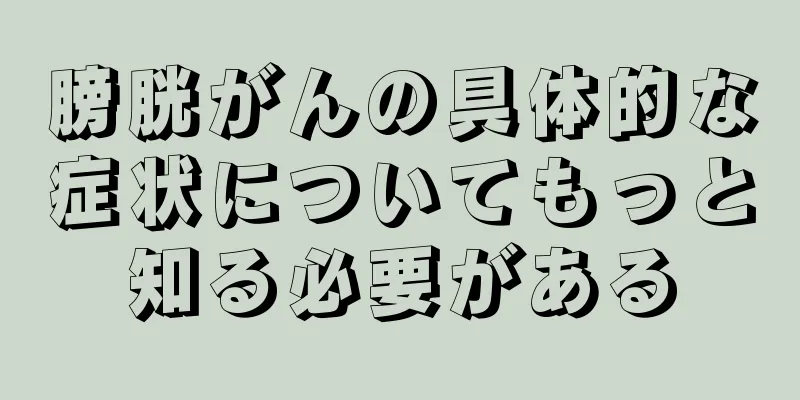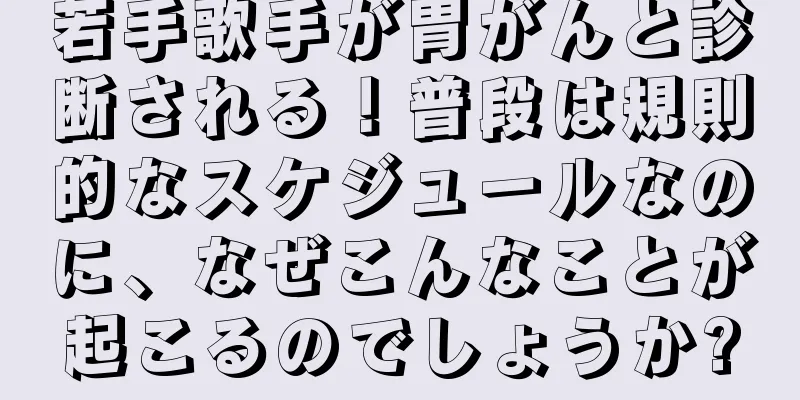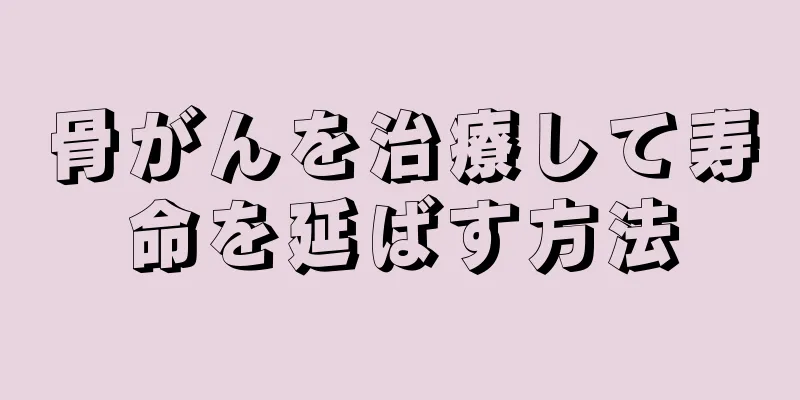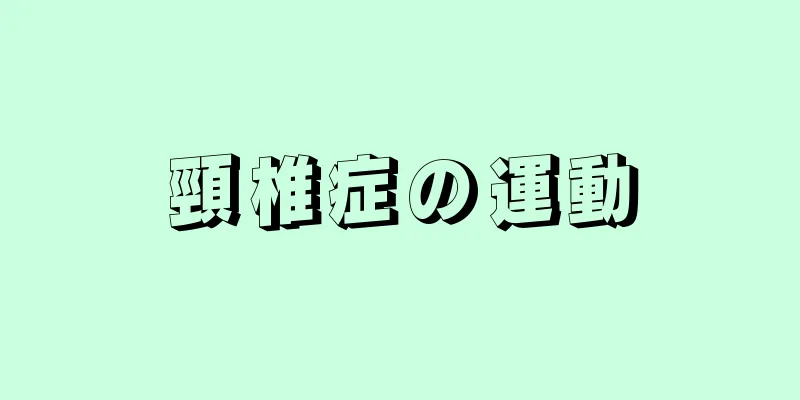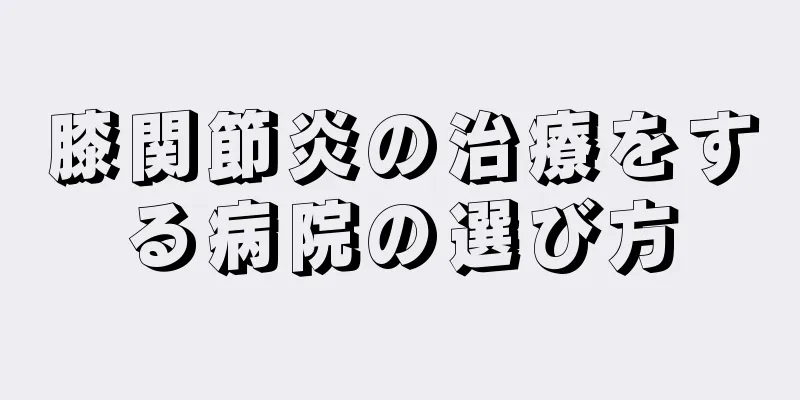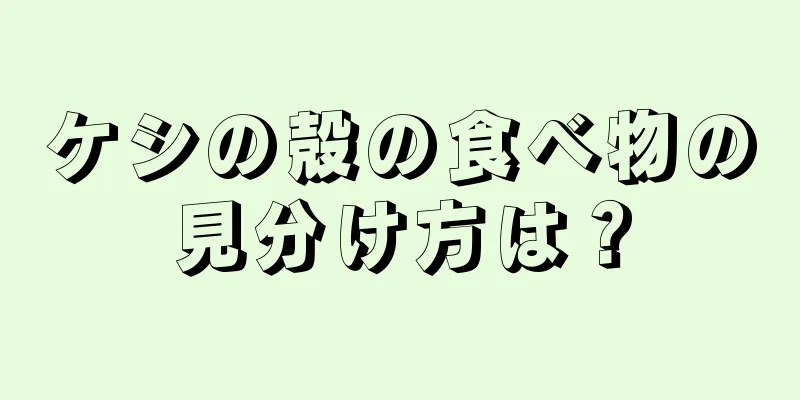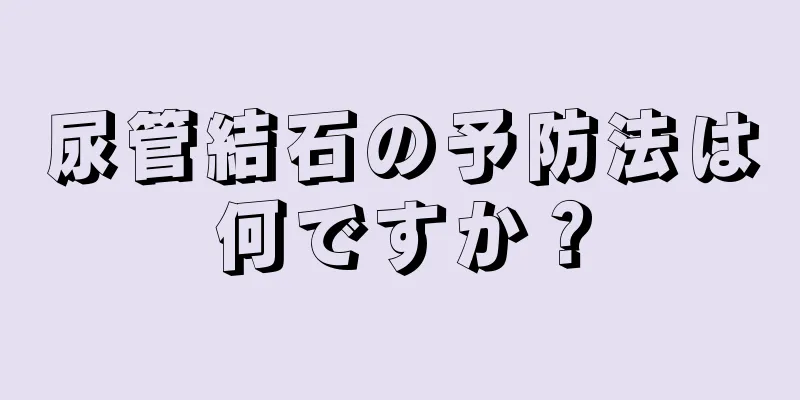火傷から回復した後、皮膚が青白くなるのはなぜですか?
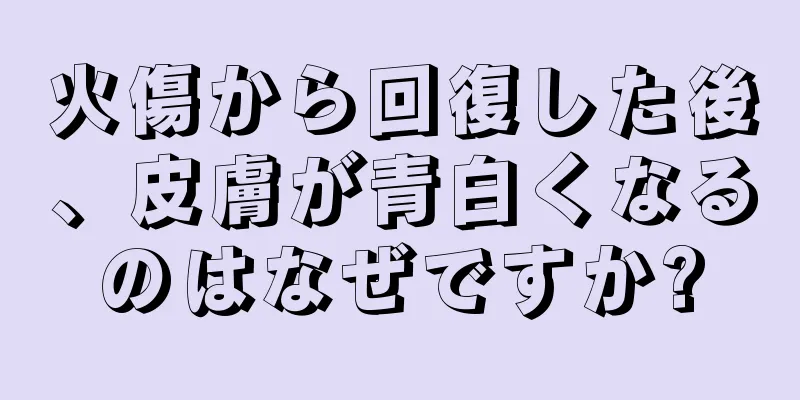
|
火傷ややけど後の傷の回復は誰もが心配する問題です。結局、もともと滑らかな肌に傷が残ることの方がみんな気にするのです。醜い傷跡が残りますか?後期段階での創傷ケアの程度が、創傷に傷跡が残るかどうかを直接決定します。傷の回復が進むにつれて、傷の回復部位の皮膚が白くなることがあります。これはなぜでしょうか? 1. 皮膚の組織構造は比較的複雑です。皮膚の最も外側にある硬く感じる層を真皮といいます。真皮の下には皮膚やその他の組織の層があります。火傷や熱傷はある程度真皮にダメージを与えます。真皮は時間の経過とともにゆっくりと新しい肉を成長させ、新しい肉の色は以前の皮膚とは確実に異なります。 2. 傷跡から新しい組織が成長します。新しい組織は紫外線にさらされることなく成長するので、肌の色は非常に白くなります。肉眼では、周囲の皮膚との鮮明なコントラストが見られます。これは正常な現象であり、傷の組織が良い方向に発達していることの証明でもあります。 3. 新しい白い肉組織が成長した後、誰もが直面する問題は、瘢痕増殖が起こるか、瘢痕が非常にかゆくなることです。瘢痕増殖を防ぐためには、瘢痕組織が外側に成長し続けるのを防ぐために、毎日決まった時間に一定の強度でマッサージする必要があります。さらに、エッセンシャルオイルマッサージは傷跡のかゆみの症状を和らげることもできます。 瘢痕組織の回復期間中は、食習慣を特別に改善する必要もあります。濃い味が好きな友達は注意が必要です。傷跡の回復期間中は、非常に辛い唐辛子や醤油などの食べ物の摂取を避けてください。これらの食品は瘢痕組織の治癒を不十分にします。さらに、さまざまな果物に豊富に含まれるビタミンをさらに補給する必要もあります。ビタミンが豊富なこれらの果物は、皮膚組織の成長を促進し、肌をより滑らかで白くします。 |
推薦する
クコの実は東洋の魔法の果物です。効果を得るには毎日どれくらい食べればよいのでしょうか?
日常生活では、クコの実でお茶を淹れている人を見かけることはよくありますし、友人のほとんども、クコの実...
ニンニクの芽の選び方
ニンニクの芽は、ニンニク苔、ニンニクの毛、青ニンニクとも呼ばれ、一定期間成長した青ニンニクの苗です。...
腸閉塞の食事療法では何に注意すべきでしょうか?腸閉塞には4つの食事タブーがある
腸閉塞の治療後は、食事にさらに注意を払う必要があります。腸閉塞の手術や薬物治療後は、絶食時間に気をつ...
リュウガンを食べ過ぎるとどうなりますか?
まず体温リュウガンはローレルとも呼ばれます。食べ過ぎると喉の痛みや炎症を起こしやすくなります。さらに...
寿命が短い男性には、飲酒時に共通する 6 つの特徴が見られます。6 つすべてに当てはまる場合は、健康診断を受ける必要があります。
アルコールは発がん性物質として知られています。過度の飲酒は脳の呼吸中枢を抑制し、呼吸停止を引き起こし...
昆布を食べることの4つのタブー
昆布は抗放射線効果があることから、最近最も人気のある料理となっています。昆布には、抗放射線作用以外に...
骨肥大の原因は何ですか?
骨肥大は主に中高年に発生します。それは非常に有害な病気です。発生した場合の主な症状は痛みです。適切な...
女性の肺がんの原因はキッチンの煙ですか?
一般的に、女性は男性よりも肺がんになるリスクがはるかに低いと考えられています。実際、これは主に、男性...
菊茶と蜂蜜を一緒に飲むとどんな効果があるのか
菊茶は私たちの生活の中で非常に一般的なお茶飲料であり、多くの人が定期的に飲んでいることは誰もが知って...
網膜血管炎による失明を防ぐ方法
網膜血管炎による失明を防ぐには?目は人体の非常に重要な部分です。しかし、現代では多くの人が眼を守る意...
気管支癌の初期症状は何ですか?
気管支癌の初期症状は何ですか?気管支肺がんは、気管、気管支、肺に発生する悪性腫瘍です。初期段階では、...
尿道炎は治りますか?
尿道炎はよくある炎症で、女性の心身の健康に大きな影響を与えるため、早めに治療する必要があります。それ...
伝統的な中国医学は坐骨神経痛をどのように治療しますか?
坐骨神経痛は、仕事中に長時間座っている人によく見られる病気です。そのため、坐骨神経痛を治す方法を知り...
外痔核ケアの最も包括的なガイド
外痔核に対する看護措置も治療法の一つと言えますが、看護はあくまで補助的な治療であり、一般的に病気を治...
高麗人参の効能の概要
高麗人参は素晴らしい抗ストレス薬ですストレスは、感情的な緊張を引き起こし、体の代謝を変化させる要因で...