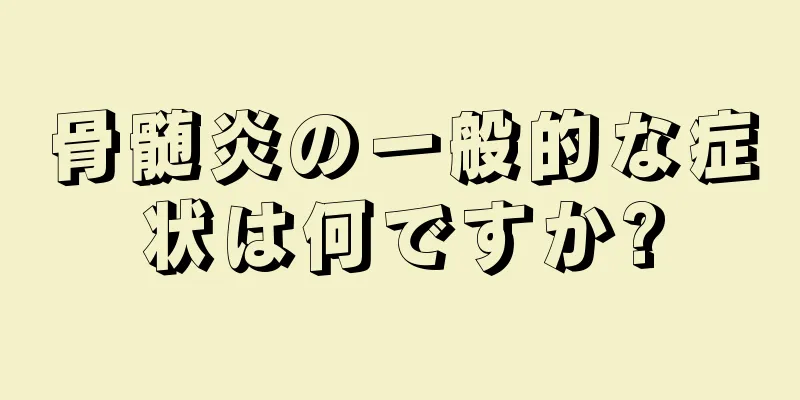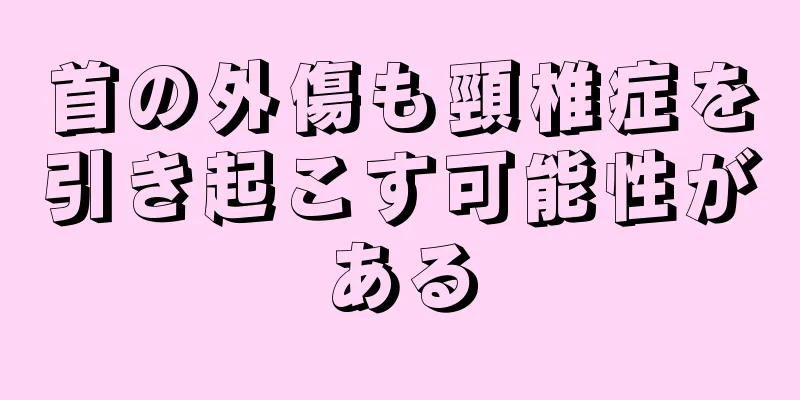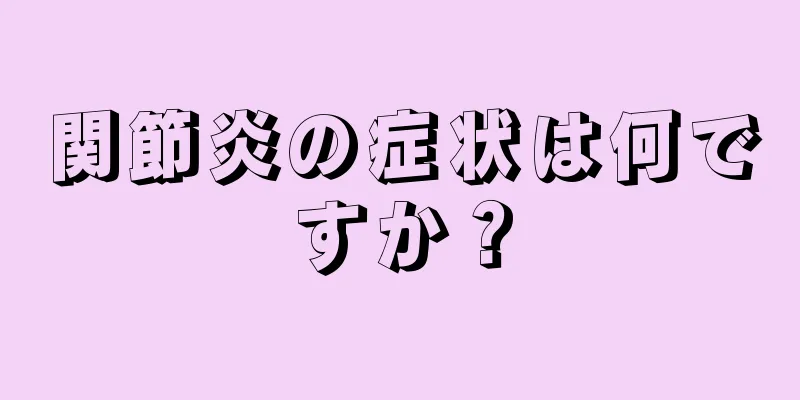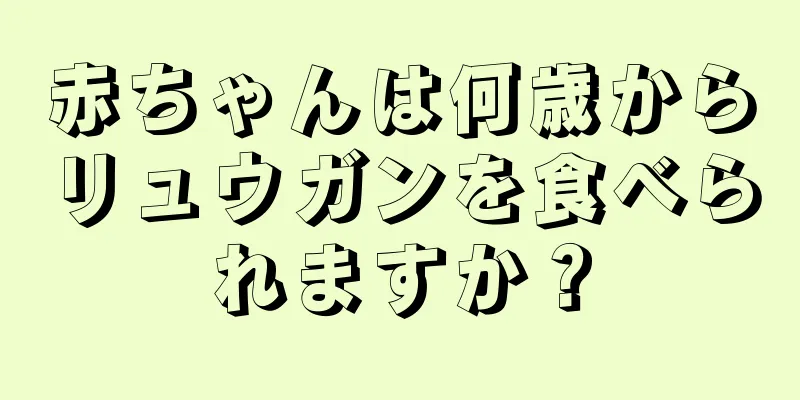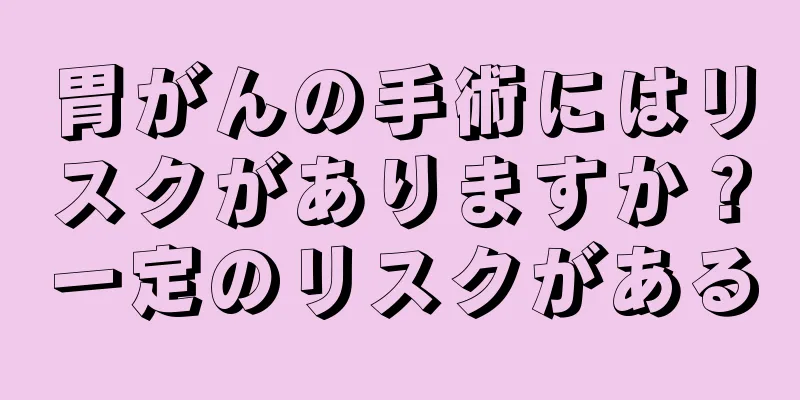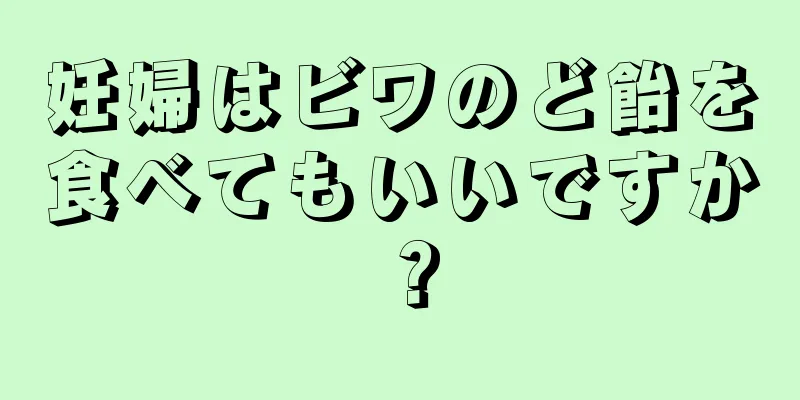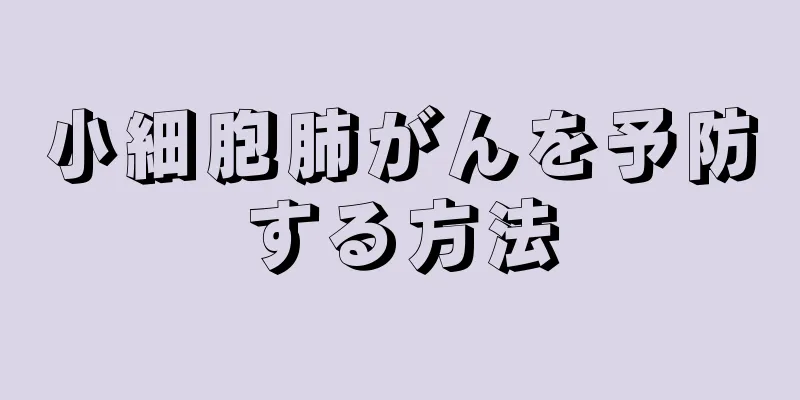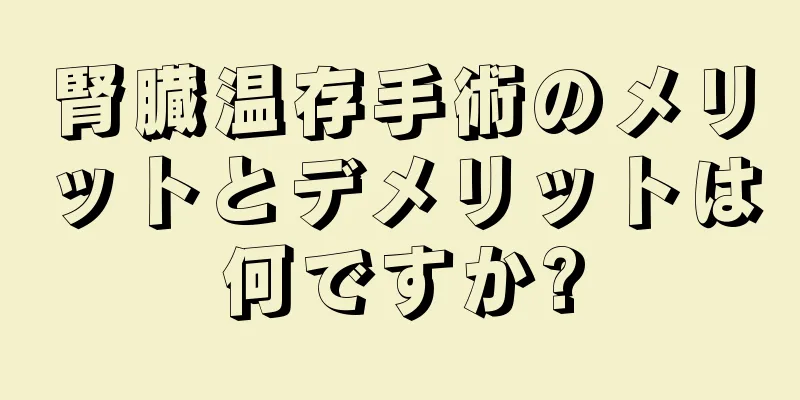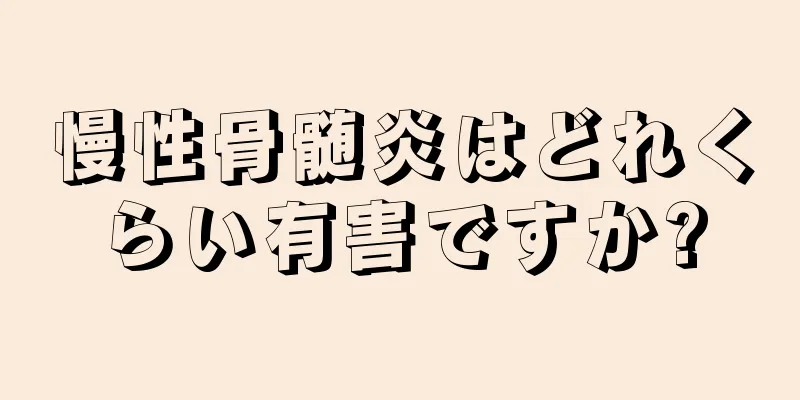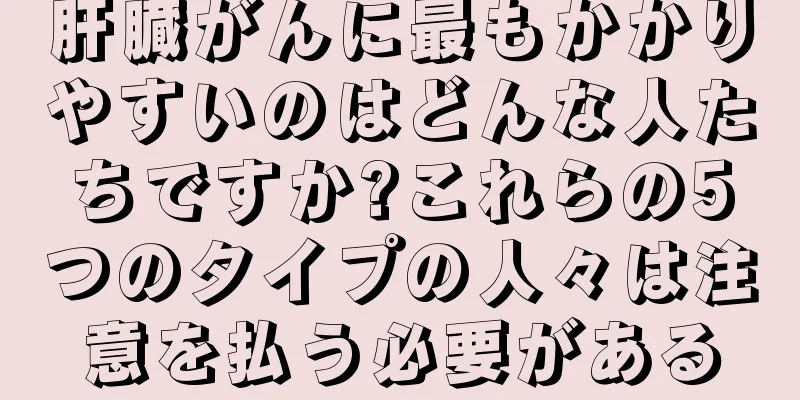皮膚がんの症状は何ですか?
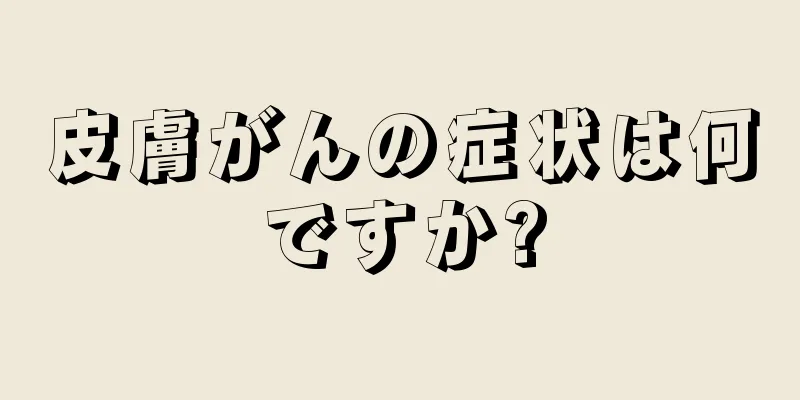
|
皮膚がんは悪性腫瘍であり、主な症状は短期間で急速に大きくなるしこりであり、その後に再発性の皮膚潰瘍やカリフラワー状腫瘍が発生します。生検が主な病理診断方法です。皮膚がんの場合、拡大切除が第一選択です。転移性皮膚がんが外科的に治療できない場合は、ヨウ素 125 粒子放射線療法またはアルゴンヘリウム冷凍凝固療法が用いられます。同時に、補助的な外部放射線療法と化学療法も必要です。 皮膚がんの治療 皮膚がんには主に 3 つの種類があり、それぞれ治療法が異なります。皮膚基底細胞がんは皮膚の表層に位置し、広範囲の浸潤や転移病変はありません。主に広範囲切除術で治療します。悪性度は比較的低く、治療効果も非常に良好です。 2 番目のタイプは皮膚扁平上皮癌で、皮膚のしこりやカリフラワー状のしこりとして現れることがあります。皮膚扁平上皮癌は生検病理学によって診断されます。局所リンパ節転移が起こる可能性があり、リンパ節洗浄、術後の放射線療法および化学療法が必要になります。 3 番目のタイプは悪性黒色腫であり、主に黒色の腫瘍が繰り返し破裂し、治癒しないという症状で現れます。手術が可能な場合は、まず手術を行い、その後、生物学的免疫療法、標的療法などと連携する必要があります。悪性度が比較的高く、治療効果は最悪です。 皮膚がんは治りますか? 皮膚がんは、ゆっくりと進行し、一般的に影響が小さい一般的な皮膚悪性腫瘍です。臨床病理学と生検によって診断を確定することができます。この病気は主に手術で治療されますが、手術の際には手術の切除縁にがん細胞が残っていないか注意する必要があります。手術後は病状に応じて放射線治療が必要かどうかが判断されます。ほとんどの皮膚がんは適切に治療すれば治癒できます。悪性黒色腫などの一部の皮膚がんは予後が悪く、手術後に放射線療法と化学療法を組み合わせて治療する必要があります。生存時間を改善します。 |
推薦する
大腿骨頸部骨折、6ヶ月経っても治らない
大腿骨頸部骨折、6ヶ月経っても治らない大腿骨頸部骨折が6か月間治癒しません。これは正常な反応である可...
各種ドライフルーツの栄養価と効能
1. ピーナッツは皮膚病を予防します。ピーナッツにはビタミンB2が豊富に含まれており、これは中国人の...
肺がん患者のケアでは何に注意すべきでしょうか?肺がんの看護における4つの注意事項
肺がん患者のケアにおいてどのような点に注意すべきかは、多くの人が関心を持つ問題です。専門家によると、...
これら4種類のナッツは食べてはいけません!
これら4種類のナッツは食べてはいけません! 1. カビの生えたナッツは発がん性がある多くのナッツは、...
肺がん2cmはどの段階ですか?
2 cm の肺がん腫瘍がどのステージに属するかを正確に判断することは不可能です。主な理由は、肺がんの...
初期の肝臓がんは治癒できますか?治癒効果が得られる
肝臓がんは早期に治療すれば治癒可能です。がんを早期に発見し、早期に治療すれば、腫瘍を除去し、細胞の拡...
尿道炎を予防するには?
ご存知のとおり、尿道炎は深刻な泌尿器疾患です。尿道炎を患うと、尿路の安全性が深刻に脅かされ、不妊症に...
胃がんの腹膜転移はどのように検査すればよいのでしょうか?これらの項目をチェックする
胃癌の腹膜転移は末期症状であり、腹腔内温熱灌流化学療法と経口化学療法薬によって制御できます。腹水が形...
遺伝は一般的に頸椎症の主な原因である
一般的に遺伝が頸椎症の主な原因であり、この要因も比較的よく見られます。では、頸椎症の他の原因は何でし...
頸肩腕症候群と五十肩の違い
頸肩腕症候群と五十肩の違い:首と肩の症候群とは、首と肩の症候群を指します。首肩症候群と五十肩の違いは...
胸膜炎には通常どのような薬が使用されますか?
胸膜炎には一般的にどのような薬が使われますか?胸膜炎はよくある病気です。胸膜炎を患っている場合、胸の...
胆嚢ポリープのさまざまなタイプの症状
胆嚢ポリープとはどんな病気ですか?胆嚢ポリープとは何ですか?胆嚢ポリープの症状は何ですか?胆嚢ポリー...
女性不妊症の原因となる卵巣の炎症:臨床症状は?
女性不妊症の女性要因には、外陰部、膣、子宮、卵巣の発育異常などの先天性発育異常、排卵障害、女性卵管閉...
尿路感染症における一般的な食事タブーの簡単な分析
尿路感染症の食事では避けなければならない食品がいくつかあり、それらは尿路感染症の症状に非常に悪影響を...
腎臓結石を予防するには?
腎臓結石を予防するには?腎臓結石は、一般的に、水分を多く摂取し、食生活を調整し、運動するなどして予防...