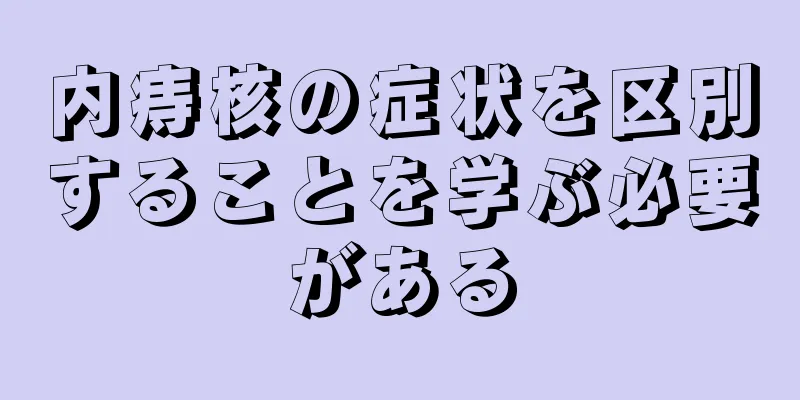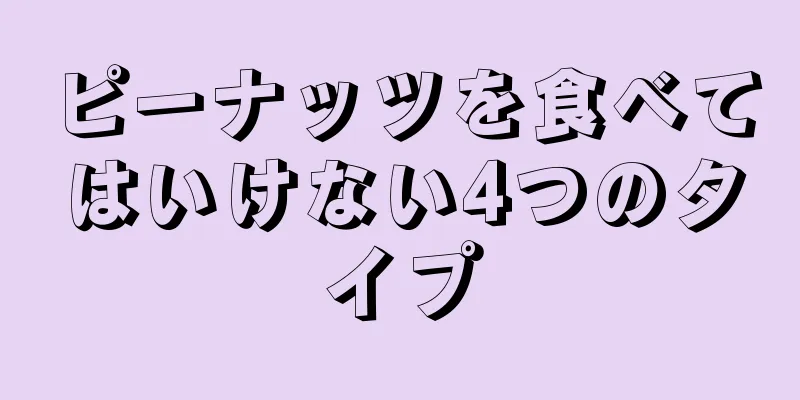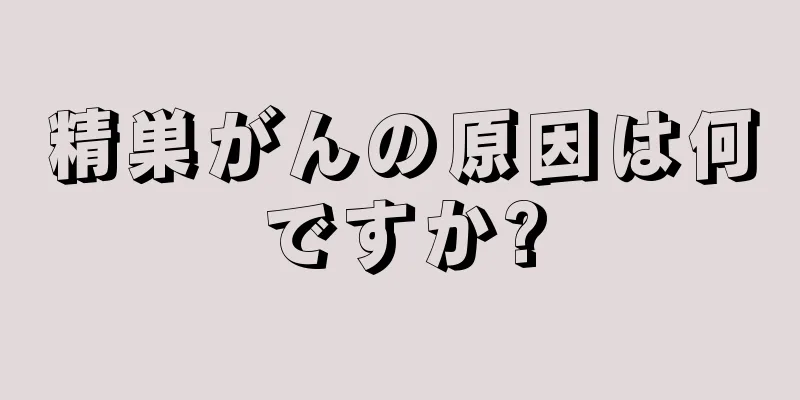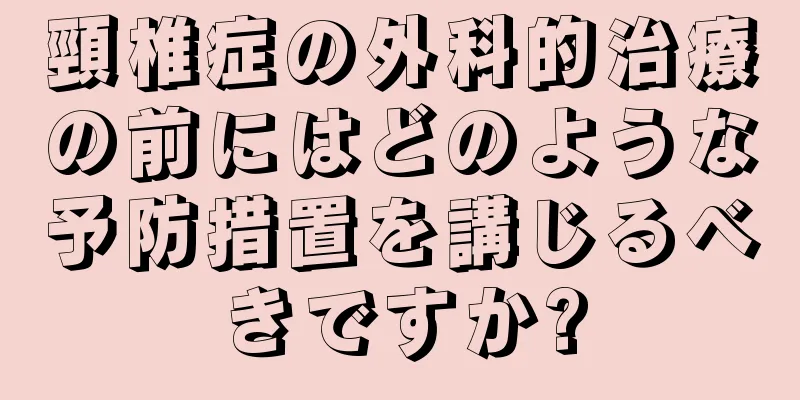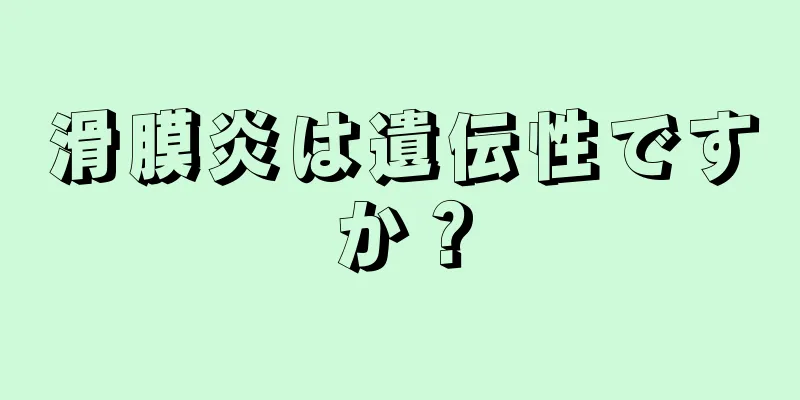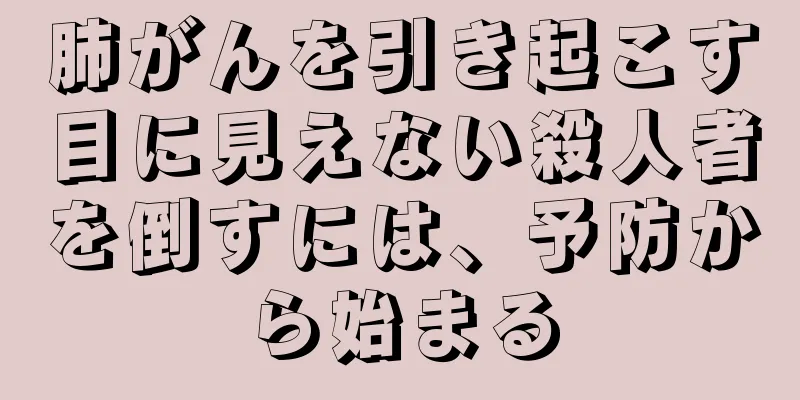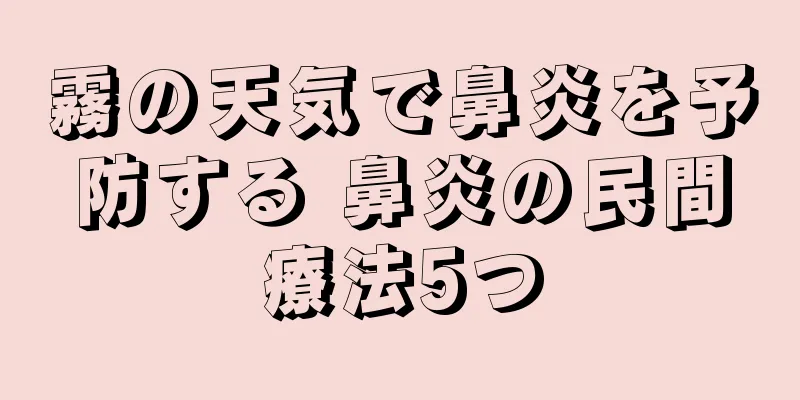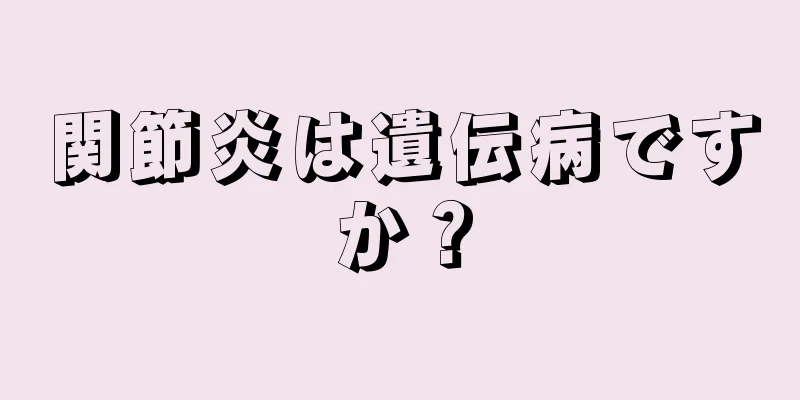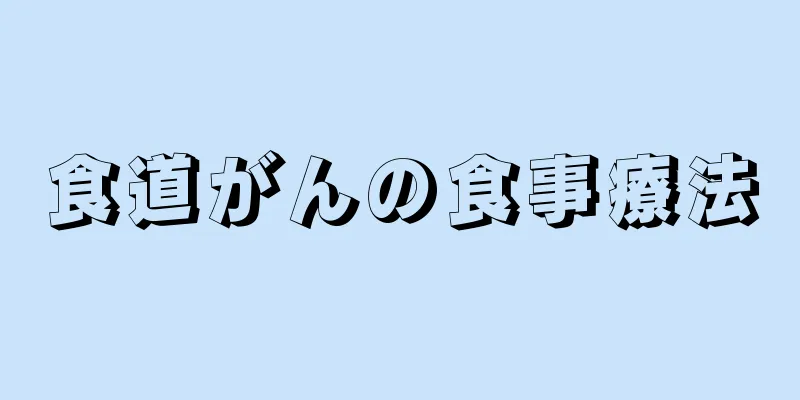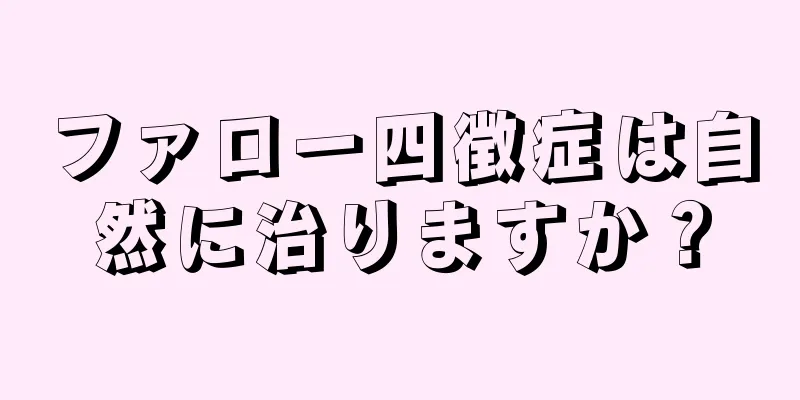小細胞肺がんの看護知識
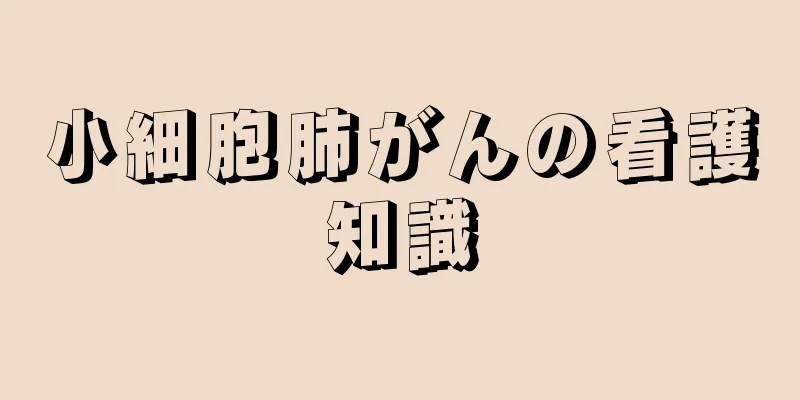
|
小細胞肺がんの看護の常識は何ですか?小細胞肺がんと診断されると、がん細胞のほとんどが転移して広がっており、治療が困難になります。患者にとっては症状を改善し、生活の質を向上させることの方が重要です。そこで今日は、小細胞肺がんの看護の常識について見てみましょう。 1. 食事は豊富で、多彩で、軽くて栄養があり、主に肉粥、魚粥、卵粥、ハトムギ粥、ユリ粥、クコの実などのさまざまな粥やスープ、果物や新鮮な野菜で構成されています。 2. 自力で動くことができない患者が、定期的に寝返りを打ったり、毎日手足をこすったりマッサージしたりできるように支援します。圧迫されている部分を紅花アルコールでこすると、床ずれを防ぐことができます。 3. 痛みを抱える患者の場合、痛みの緩和の要求を可能な限り満たし、麻薬性鎮痛剤の依存性を恐れずに生活の質を向上させる必要があります。 4. 軽音楽、民族音楽、ベートーベンの交響曲第5番などを聴くことで、心身をリラックスさせ、生活の質を向上させることができます。 5. 患者の死への恐怖を取り除くために、より精神的な慰めを提供する。患者の配偶者や親族に、患者を愛撫し、抱擁し、優しく話し、家族の事柄についてもっと話し合い、患者に愛情と愛着を表現し、家族の愛情に対する心理的欲求を満たし、死の恐怖を忘れ、それによって精神的な喜びを得るよう奨励し、訓練します。 6. 患者の呼吸、血圧、脈拍、体温、意識の変化を注意深く観察します。異常が見つかった場合は、すぐに医師に報告し、対症療法を受けてください。 7. 軽い運動ができる患者さんの場合は、ゆっくり歩いたり、散歩したり、筋肉をストレッチしたりするのに付き添ってもらっても構いませんが、やり過ぎには注意してください。 以上が「小細胞肺がんの看護知識」の簡単な紹介でした。多くの患者さんや友人の方々のお役に立てれば幸いです。小細胞肺がんの治療においては、上記のような側面からケアを行うことで、半分の労力で2倍の効果が得られ、小細胞肺がんの患者ができるだけ早く回復できるようになります。 |
推薦する
ビタミンBについて理解する
ビタミンB?ビタミンB:ビタミンB群には多くの種類があります。健康を維持するために、それぞれが役割を...
強直性脊椎炎の原因は何ですか?
強直性脊椎炎の発症は、多くの場合、仙腸関節から始まり、徐々に脊椎および傍脊椎組織へと上方に広がります...
半月板損傷は寿命に影響しますか?
半月板損傷後、患者は正常に歩行できなくなります。アスリートが半月板損傷を負うと、通常のトレーニングが...
卵管炎の治療に服用する薬
卵管炎にはどんな薬を飲めばいいですか?卵管炎は一般的な婦人科疾患であり、女性の生殖器系に大きな影響を...
腰椎椎間板ヘルニアの主な症状は何ですか?
腰椎椎間板ヘルニアの症状は何ですか?腰椎椎間板ヘルニアが発生すると、患者は大きな痛みを感じ、日常生活...
悪性黒色腫の手術後のケアはどうすればいいですか?
悪性黒色腫に対する手術は比較的一般的な治療法です。では、悪性黒色腫の術後ケアでは何をすべきでしょうか...
下肢静脈血栓症になった場合の対処法
まず、下肢静脈血栓症は臨床的に非常に重篤な病気です。医学は常にこの病気を非常に重要視してきました。合...
リュウガンとナツメの違いは何ですか?
リュウガンとリュウガンの違いリュウガンはライチとも呼ばれます。多くの友人がリュウガンとライチの違いを...
女性の不妊症は平均寿命に影響しますか?
不妊症だと分かった後、多くの人はいつも急いで治療を求めます。日常生活では、不妊症の発生に注意し、関連...
虫垂炎に効く抗炎症薬は何ですか?虫垂炎の危険性は何ですか?
虫垂炎については皆さんもよくご存知だと思います。虫垂炎が発生すると、激しい腹痛の症状が伴い、患者に大...
胃がんの手術にはどれくらいの時間がかかりますか?通常2~3時間
胃がんの手術にかかる期間は一般化できません。それは病変の範囲、手術の難易度、手術方法、医師の経験など...
冷たいベビーキャベツの作り方
冷たいベビーキャベツの作り方最近の野菜市場には、本当に圧倒されるほどたくさんの種類の野菜が並んでいま...
関節リウマチは遺伝性ですか?
現在の研究によれば、関節リウマチの原因はまだ発見されていません。現時点では自己免疫疾患としてのみ知ら...
前立腺がんの骨転移について
前立腺がんは血液転移によって体内のあらゆる組織や臓器に広がる可能性がありますが、遠隔転移の最も一般的...
食べ過ぎて運動不足は糖尿病の原因になる
糖尿病の原因は遺伝的要因のほか、生活習慣や食生活の要因が多く、その中でも食生活の要因が大きな割合を占...