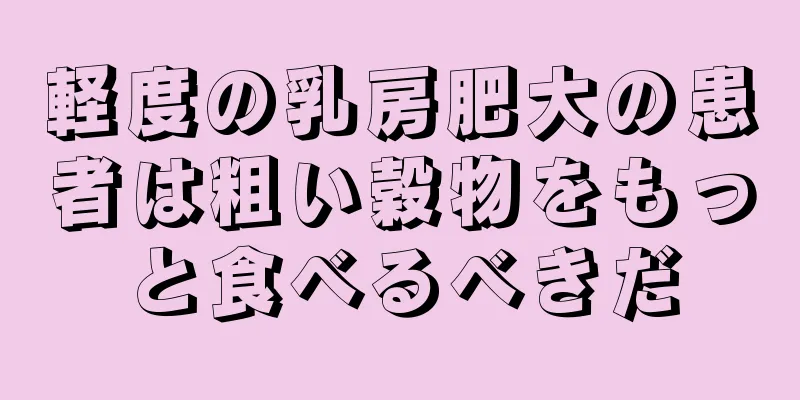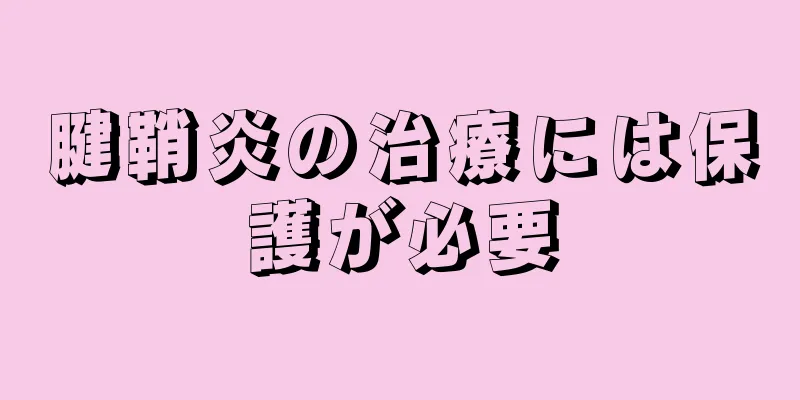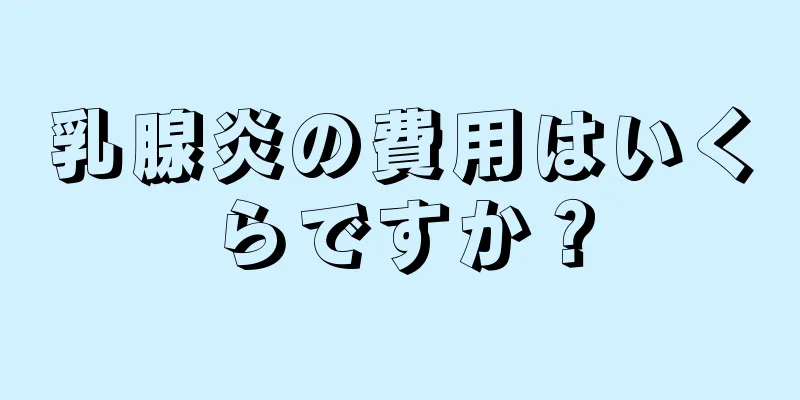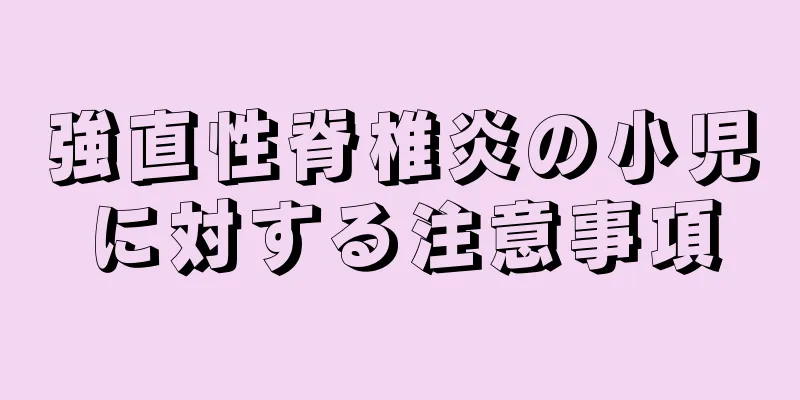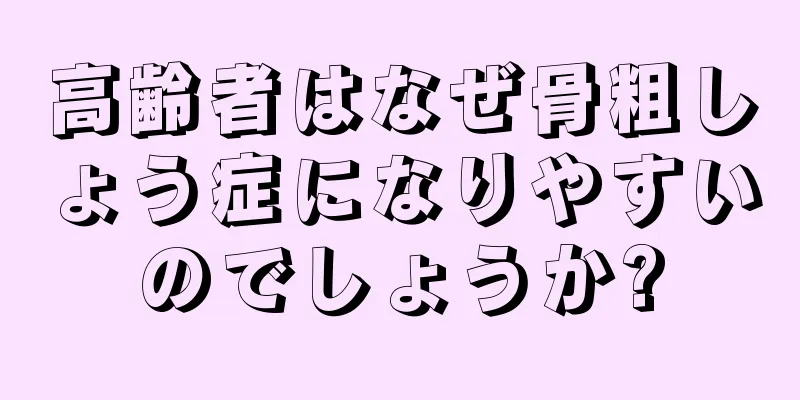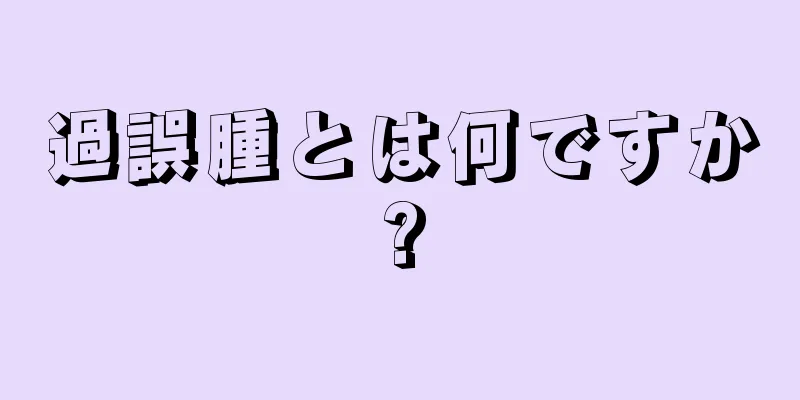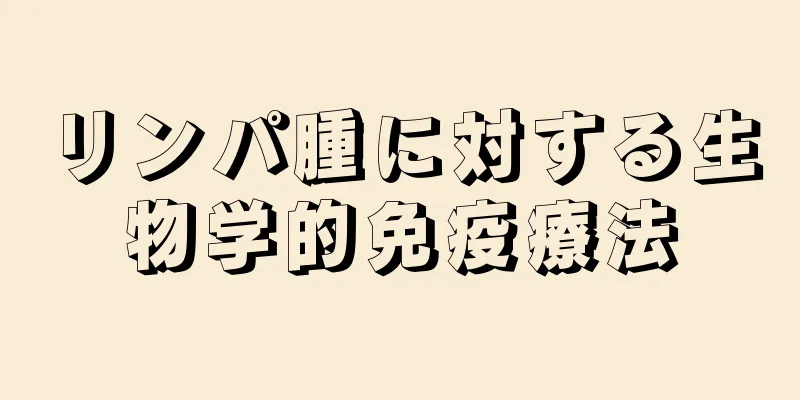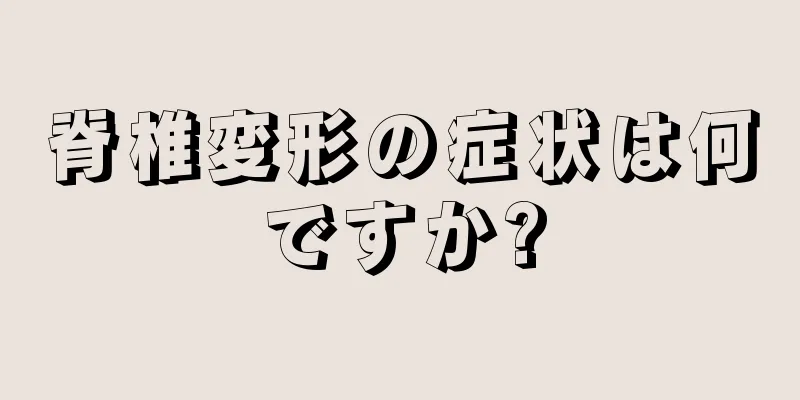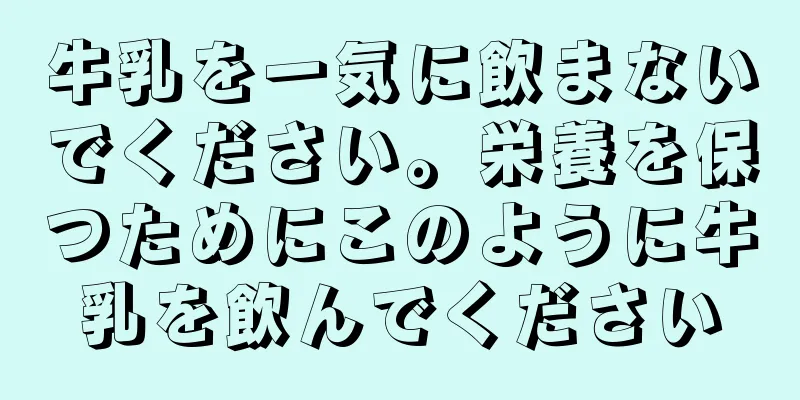黄体機能不全患者が鶏肉を食べる際の注意事項
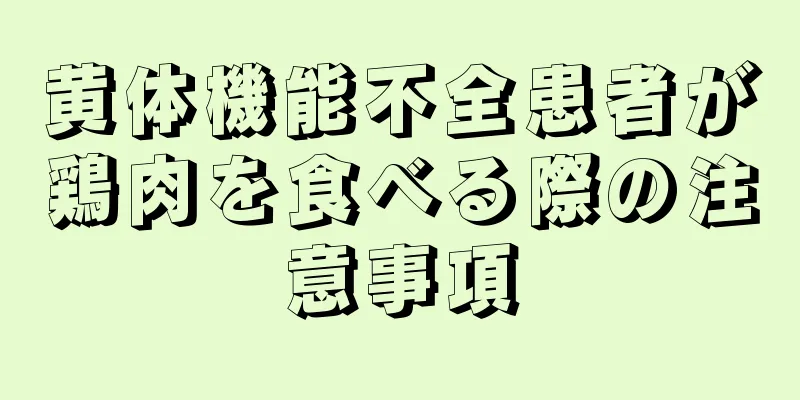
|
黄体機能不全の患者は鶏肉を食べることで脾臓を養い、血液を養い、腎臓を養い、精気を増進することができます。食べる際には以下の点に注意する必要があります。 1. 鶏肉を食べるときは、一緒にチキンスープを飲む必要があります。鶏の頭を食べるのは、年齢に関係なくタブーです。鶏の腰の先を食べるのもタブーです。 2. 鶏肉はウサギの肉と同時に食べてはいけません。鯉と同時に食べてはいけません。鶏肉は甘くて温かく、鯉は甘くて中性です。鶏肉は中を養い、陽を助け、鯉は気を和らげ、利尿を促進します。それらの性質と味は反対ではなく、それらの機能は倍増します。魚はタンパク質、微量元素、酵素、さまざまな生物活性物質が豊富で、鶏肉の成分も非常に複雑です。鶏肉と梅は相性が悪く、食べると下痢を引き起こします。 3. 鶏肉と菊は相性がよくありません。軽症の場合は患者に不快感を引き起こし、重症の場合は死に至ることもあります。鶏肉とニンニクは同時に食べないでください。ニンニクは辛くて温かくて有毒です。ガスを減らし、食べ物を排出し、風を取り除き、ウイルスを殺すのに役立ちますが、鶏肉は甘くて酸っぱくて温かいです。この2つは反対の働きをします。ニンニクは燻蒸臭があり、調味料の観点から鶏肉とは相性がよくありません。 4. 鶏肉とゴマは相性がよくありません。一緒に食べると死に至る可能性があります。鶏肉とマスタードを一緒に食べると、活力が損なわれます。マスタードは辛い食べ物で、鶏肉は温熱強壮剤なので、熱が上昇し、健康に良くありません。 5. 鶏の腎臓と犬の腎臓は相性が悪く、赤痢を引き起こす可能性があります。 ヒント:黄体機能不全の患者は、鶏と小豆のスープを食べることができます。鶏肉500〜1000g、小豆250gに水を加えて調理し、患者はスープを飲み、肉を食べることができます。 |
>>: 卵管閉塞の患者は必要に応じて手術が必要になる場合があります
推薦する
肺がんが再発した場合、どれくらい生きられますか?
肺がんが再発した場合、どれくらい生きられますか? 1. 肺がんが腺がんの場合、現在、優れた化学療法薬...
骨結核を除外するためにどのような検査を使用できますか?
私たちの人生において、病気は避けられません。骨結核を例に挙げてみましょう。この病気は人生において非常...
腎臓結石の治療法は何ですか?
腎臓結石の発生は患者に大きな害をもたらします。腎臓結石の治療法は何ですか?これがほとんどの患者が懸念...
「蒸して」食べるのに適した果物6種
通常、私たちは果物を洗ったり、フルーツサラダにして食べたりします。しかし、果物の多くは生で冷たい食べ...
ブドウの効能と機能
ブドウは私たちの生活に欠かせない果物です。栄養価が非常に高く、ビタミンや水分を多く含んでいます。甘い...
プーアル茶には本当に血中脂質を下げる効果があるのでしょうか?
プーアル茶は中国で最も古くから伝わる有名なお茶です。プーアル茶は後発酵茶で、飲用古茶とも呼ばれていま...
足の骨折が治った後、歩いた後に足の裏に痛みが出る
足の骨折が治った後、歩いた後に足の裏に痛みが出る足の骨折が治った後、回復までの時間が短い、過度な運動...
卵管閉塞を防ぐ6つのヒント
卵管閉塞は女性不妊症の原因となり、本人や家族に大きな影響を及ぼします。そのため、正しい方法で積極的に...
甘酸っぱいニンジンとキノコとベビーキャベツ
甘酸っぱいニンジンとキノコとベビーキャベツ材料ベビーキャベツ 2 個、白キノコ適量、にんじんピューレ...
甲状腺がんが声帯損傷を引き起こした場合の対処法
甲状腺がんは、甲状腺濾胞上皮または濾胞傍細胞から発生する悪性腫瘍です。声帯損傷の原因は、外科的要因、...
腰痛患者は腰のツボをマッサージすると良い
腰の筋肉が緊張している患者は、腰のツボをマッサージすることで症状を緩和することができます。腰のツボを...
大腿骨頭壊死の治療方法
大腿骨頭壊死は一般的な骨関節疾患の一つで、大腿骨頭の破壊によって引き起こされる骨虚血です。股関節に重...
女性不妊の原因に注意を払うことで、いつでもこの病気を予防することができます
今日、女性の不妊症に悩む人が増えており、それが生活に多大な不便をもたらし、深刻な場合には結婚生活を破...
専門家が女性不妊症の主要検査項目8つを紹介
女性不妊は誰もが気になる問題ですが、患者としてはまず女性不妊の検査項目を理解しなければなりません。こ...
肝血管腫の治療原則は何ですか?
誰も肝臓に害を及ぼすことを望んでいませんが、肝血管腫を含め、人々の肝臓に害を及ぼす可能性のある病気は...