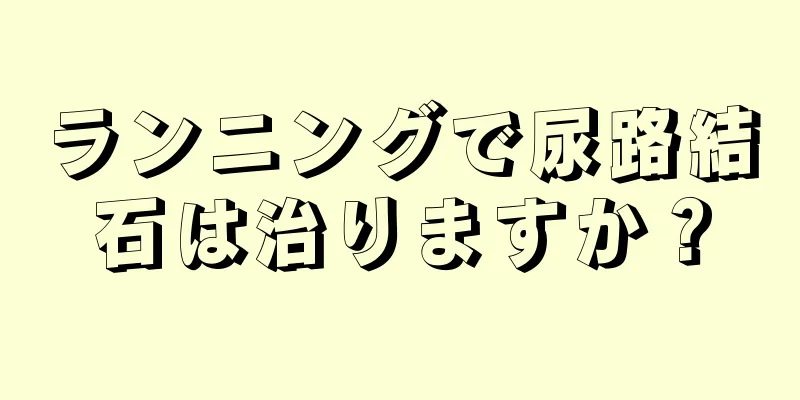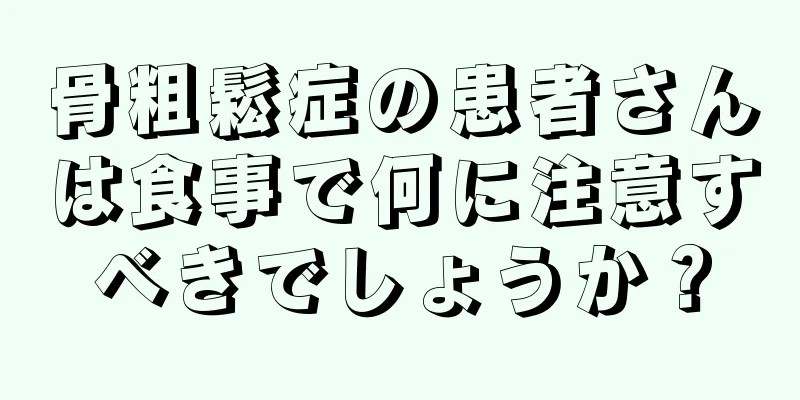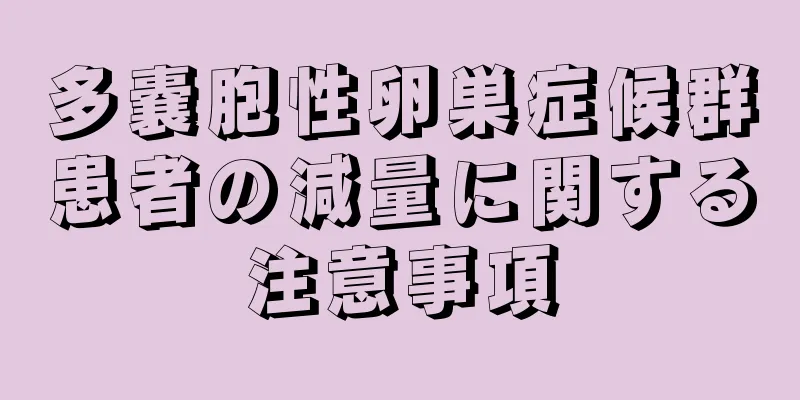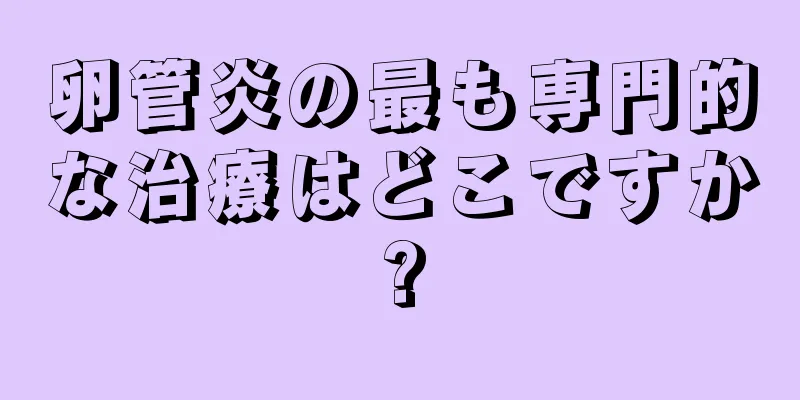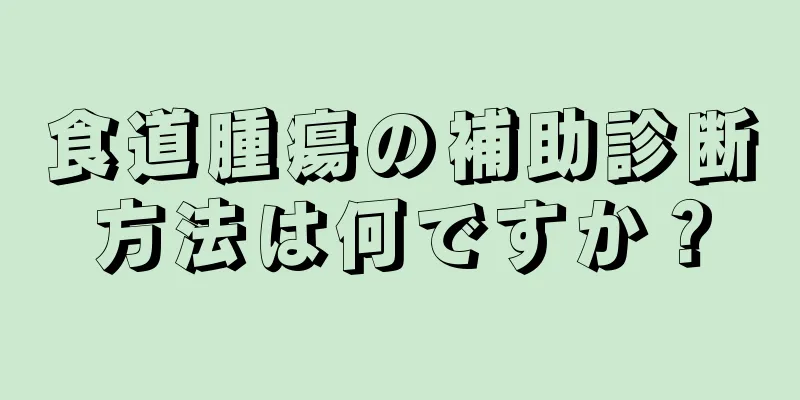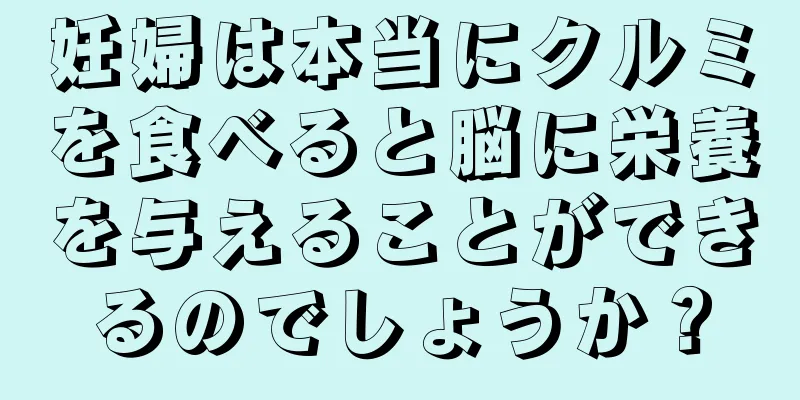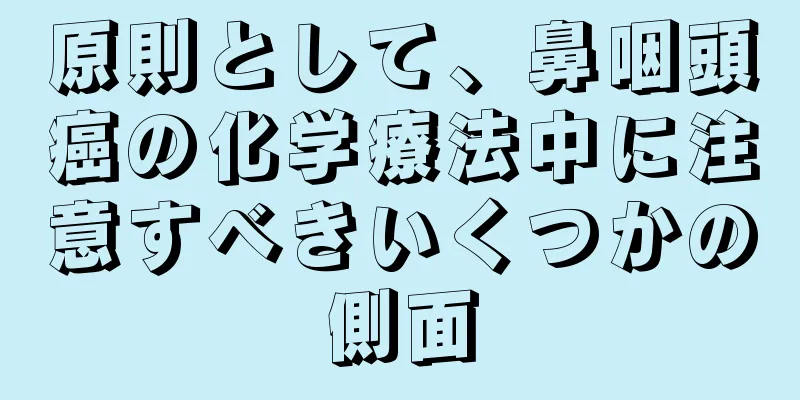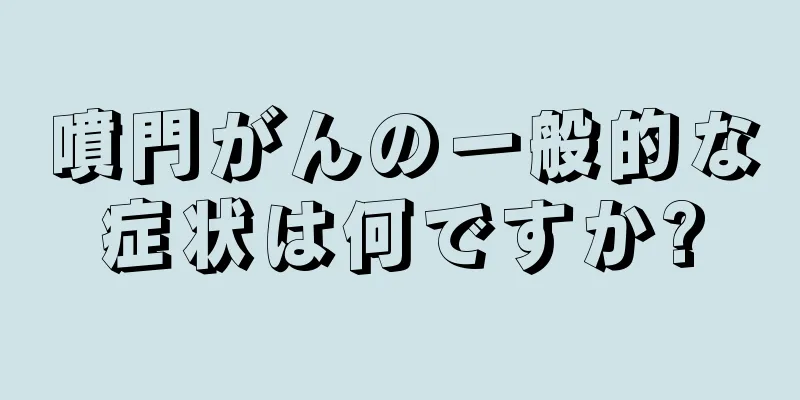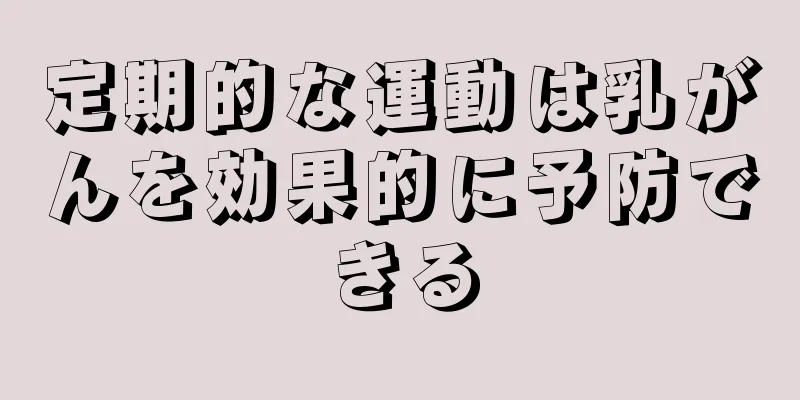痔の手術から完全に回復するには3か月かかりますか?
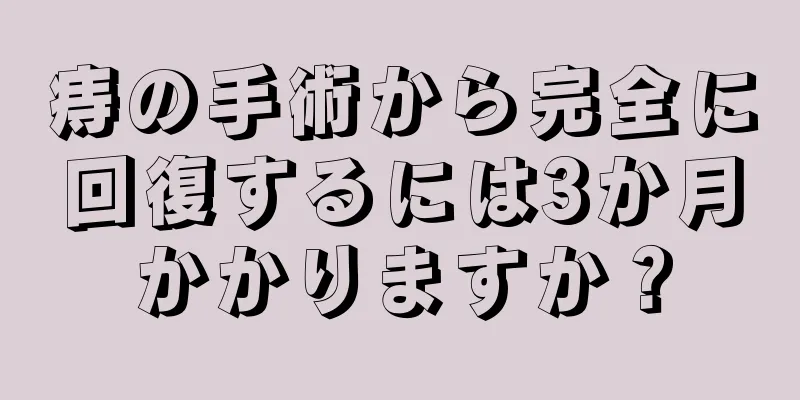
|
痔の手術から完全に回復するには3か月かかりますか? 通常、痔の手術から完全に回復するには 3 か月はかからず、1 か月程度で済みます。痔の手術後の回復時間は、痔の手術方法や患者の症状の重症度など、多くの要因の影響を受けます。一般的に、痔の手術後の回復には約1か月かかります。 痔の手術から完全に回復するには3か月かかりますか? 1. 痔の手術後、回復するのに通常 3 か月はかかりません。通常の回復期間は約1か月です。局所的な傷が大きすぎる場合や、患者が瘢痕形成体質である場合は、それに応じて回復時間が長くなることがあります。 2. 一般的に、PPH や RPH を含む低侵襲痔核手術後、患者は手術後約 2 週間で通常の生活や仕事に戻ることができます。 3. 外痔核切除術や内痔核結紮術などの痔核に対する開腹手術は、肛門周囲に手術切開があるため、開腹手術となります。開腹手術の治癒時間は比較的長く、手術後に完全に治癒する場合があります。 痔の手術後の注意事項: 1. 手術後の最初の日は、お粥、野菜、バナナ、ドラゴンフルーツなど、便をできるだけ柔らかくして排便をスムーズにする、消化が良く便をあまり出さない食べ物を摂取するようにしてください。一般的には、排便が正常に行われれば退院とみなされ、基本的には2~3日で帰宅が考えられます。 2. 排便後は毎回、温水と1:5000 過マンガン酸カリウム溶液で座浴を行い、肛門を清潔に保ち、感染を予防します。洗浄後は、傷の治癒を促進するために軟膏を塗る必要があります。 3. 手術後、完全に回復するまでには通常 2 ~ 3 週間かかります。肛門は収縮する機能を持つ必要があり、縫合が多すぎると肛門機能が部分的に失われるため、手術中に大量に縫合することは推奨されません。完全な治癒を達成するためには、手術後 2 ~ 3 週間経過してから患者を追跡し、肛門機能を適時に観察することが推奨されます。 |
推薦する
神経膠腫が治癒する可能性はどれくらいですか?
神経膠腫の治療には多くの方法があり、主に外科的治療ですが、後期には放射線療法や化学療法が補助的に行わ...
皮膚がんの症状は何ですか?
皮膚がんについてあまり聞いたことがない人も多いかもしれませんが、実は私たちの生活の中で皮膚がんに苦し...
骨肥大の一般的な2つのタイプとその症状
骨肥大の本質は、人間の骨の「老化」現象であり、正常な生理現象です。治療が簡単になります。骨肥大の症状...
リンパ腫は伝染しますか?
実際、リンパ腫には約 80 種類あり、そのほとんどは家族内での集積性があります。親または実の兄弟がリ...
妊婦がヤマモモを食べる場合の注意点
1. 食べ過ぎない:ベイベリーは比較的酸っぱいので、一度に食べ過ぎないようにしてください。食べ過ぎる...
喉頭がんの治療にはどれくらいの費用がかかりますか?
喉頭がんには原発性および続発性の 2 種類があります。喉頭がんの治療法は地域によって異なり、治療費も...
鼻咽頭がんの初期症状は何ですか?
鼻咽頭癌は、鼻咽頭の上壁と側壁に発生する悪性腫瘍を指します。中国は鼻咽頭がんの発生率が高い国の一つで...
プーアル茶を飲む際のよくある誤解
誤解1: お茶を長く淹れすぎる多くのお茶は長時間の抽出には適しておらず、ゆっくり抽出するのに適したお...
歯を傷つけずにヤマモモを食べる方法はこれです!
歯を傷つけずにヤマモモを食べる方法はこれです! 1. ベイベリーを食べた後はすぐに歯を磨く必要があり...
がん患者の食事療法
1. 仏手粥材料:ベルガモット15グラム、精白米60グラム、氷砂糖適量。作り方:まず仏手を炒めて汁を...
腰椎椎間板ヘルニアの症状は何ですか?
腰椎椎間板ヘルニアの症状の特徴は何ですか?これは多くの人が尋ねている質問です。専門家によると、腰椎椎...
坐骨神経痛の治療前に注意すべきことは何ですか?
坐骨神経痛の治療前に注意すべきことは何ですか?坐骨神経痛の治療前に注意すべきことは何ですか?坐骨神経...
膝関節炎の灌流療法に関する知識
膝関節洗浄は、変形性関節症、化膿性関節炎、関節リウマチ、外傷性滑膜炎など、さまざまな膝関節疾患の治療...
肺がんの治療中に注意すべきことは何ですか?肺がん治療中に注意すべき3つのこと
現代医学の継続的な進歩により、人々の健康を脅かす深刻な病気である肺がんにも治療法が確立されました。病...
肝臓がんに対する経皮的介入治療は何回必要ですか?それは個々の状況によって異なります
肝がんに対する経皮的介入治療の必要回数は、患者の状態によって異なります。月に3~4回行う必要はありま...