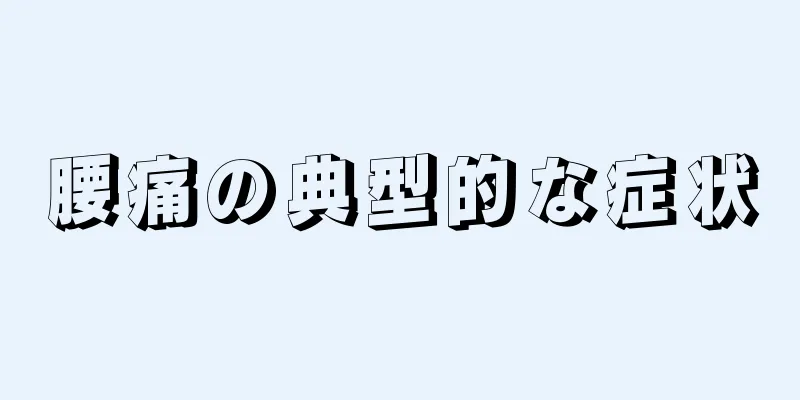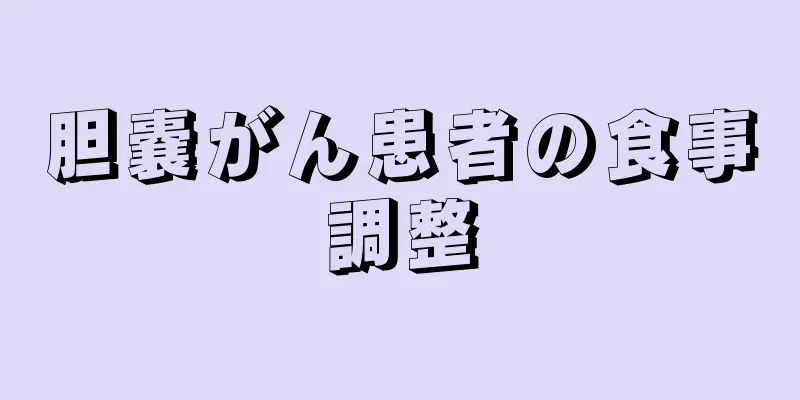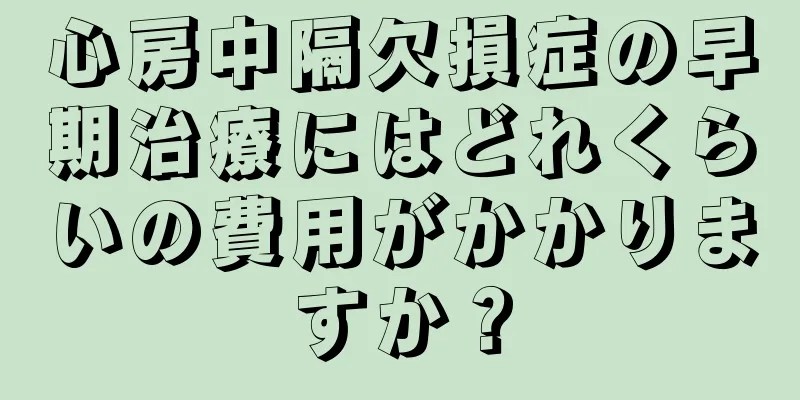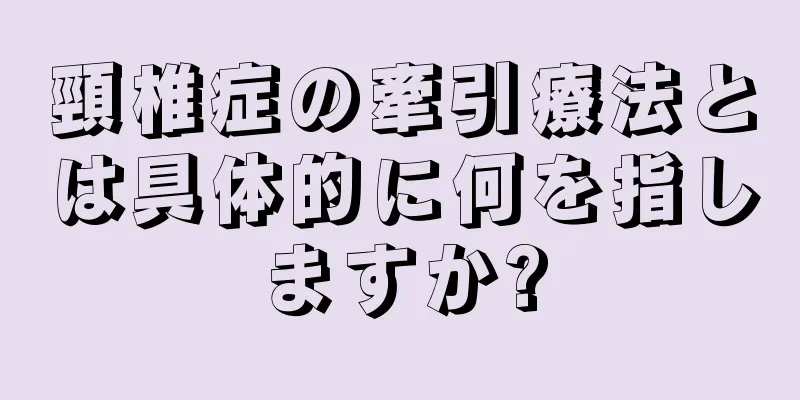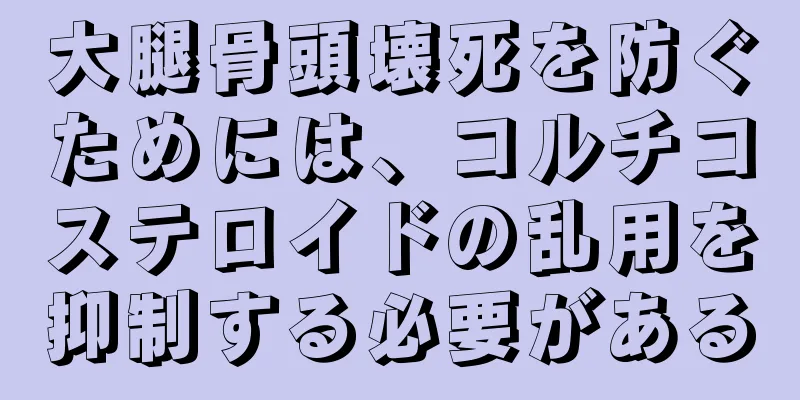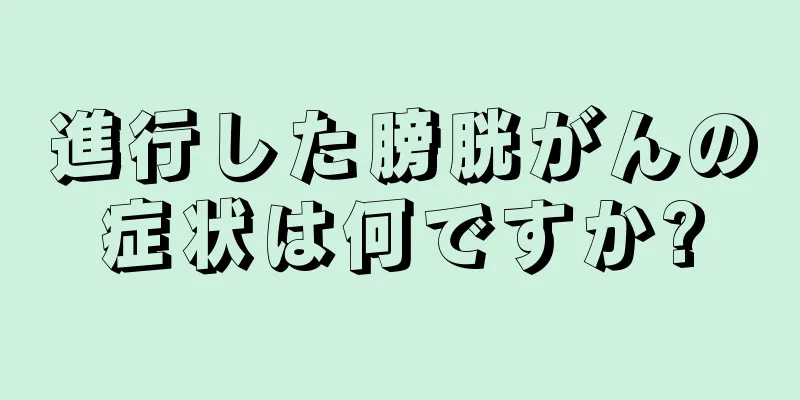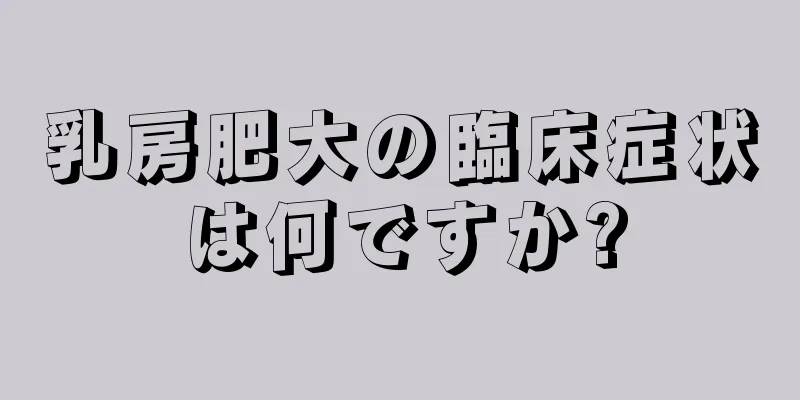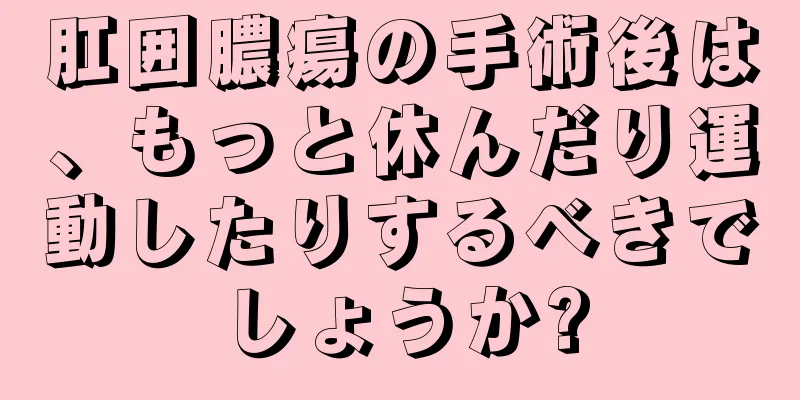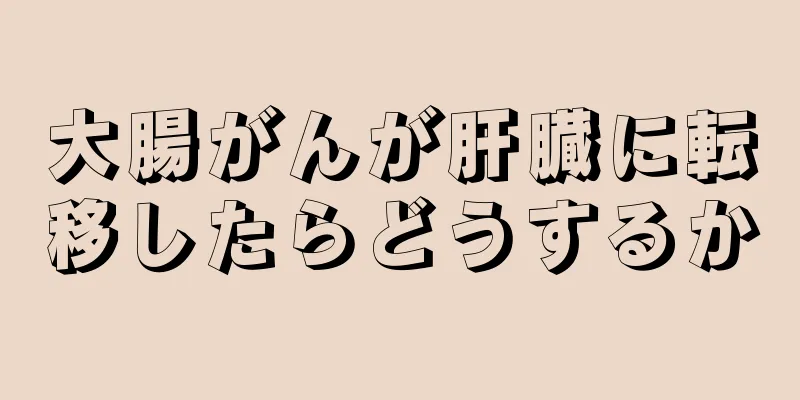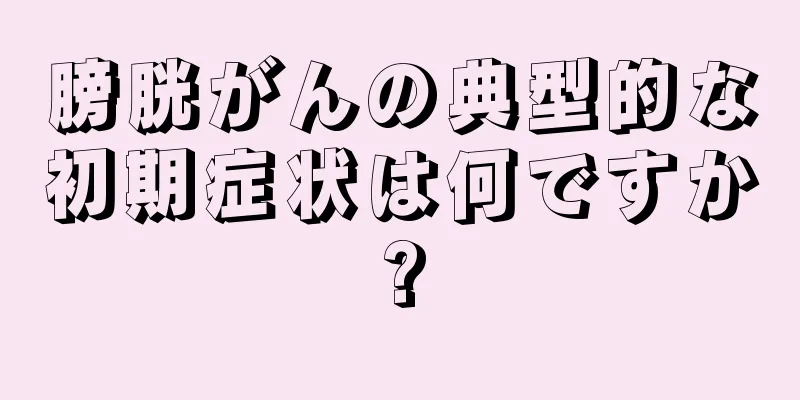無症状の腎臓結石は治療が必要ですか?
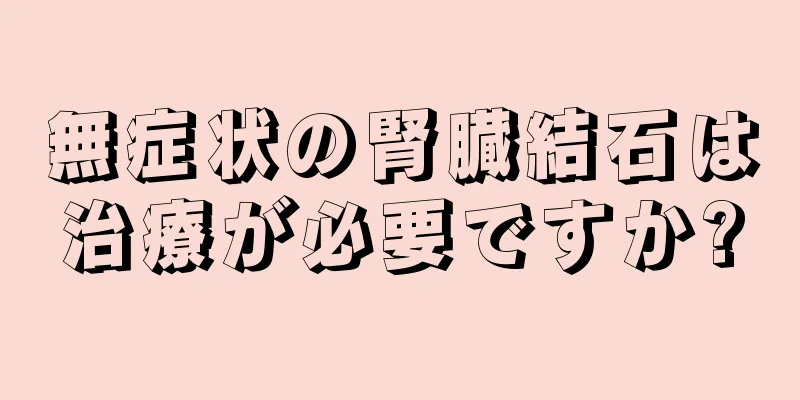
|
腎臓結石は泌尿器科でよく見られる病気です。結石が大きくなく、頻尿、排尿痛、血尿、腎臓部の痛みなどの症状がない場合は、当面治療の必要はありません。注意深く観察し、水をたくさん飲んで、テストをスキップしてください。あるいは、結石除去顆粒、腎結石除去顆粒、結石除去顆粒などの結石除去剤を適切に服用し、食事に気を付け、定期的にB超音波検査を受けることもできます。必要に応じて体外結石破砕術を実施することができます。 腎臓結石に食べてはいけない果物 腎臓結石は泌尿器科でよく見られる病気です。腎臓結石の形成には、個人の体質、体内のホルモン分泌レベル、食事や水分構成、仕事の種類、人種など、多くの要因が関係しています。腎臓結石には、結石の成分に応じて異なる予防計画が必要です。腎臓結石は、シュウ酸カルシウム結石、リン酸結石、尿酸結石、シスチン結石など、さまざまな種類に分類できることは誰もが知っています。したがって、異なる成分の結石に対する食事による予防戦略は異なります。たとえば、尿酸結石の場合は低尿酸・低プリン食が必要であり、シュウ酸カルシウム結石の場合は低カルシウム食と牛乳、大豆製品、その他の関連食品の摂取制限が必要です。腎臓結石にどんな果物を食べられるかは、結石の成分によって異なります。 腎臓結石に対する食事上のタブーは何ですか? 腎結石は腎盂、腎杯、腎臓と尿管の接合部に発生する結石です。それは、尿路閉塞、尿路感染症、地理、環境気候条件、食事、栄養などの要因に関連しています。腎臓結石はシュウ酸カルシウムの結石です。日常生活では、豆、ビート、ほうれん草、コリアンダー、イチゴ、牛肉、羊肉、犬肉など、シュウ酸カルシウムを多く含む食品を控えましょう。紅茶、タケノコ、タマネギ、ビンロウの実、そしてあらゆる種類の魚。特にエビやカニなどの魚介類は食べてはいけません。また、揚げ物を食べたり、お酒を飲んだりしないでください。 |
推薦する
肺がんのケア方法は?肺がんの科学的で正しい看護方法の紹介
いかなる病気においても治療とケアは切り離せないものです。ケアの質は病気の進行に影響します。多くの患者...
黄体機能不全の治療にはどれくらいの費用がかかりますか?
黄体機能不全は女性不妊の重要な原因の一つであり、女性の正常な仕事や生活に影響を及ぼすだけでなく、女性...
食道腫瘍の診断
誰もが治療を受けられるように、このがんを早期に発見し、早期に治療を受けたいと願う友人は多いと思います...
日常生活における尿失禁の原因
尿失禁の発生率は国民の間で常に高く、女性は尿失禁の高リスクグループです。したがって、女性の友人の尿失...
膀胱炎の病院での治療法は何ですか?
膀胱炎はすべての人の健康を危険にさらし、多くの患者を苦しめるため、病院での膀胱炎の治療法は注目に値し...
甲状腺髄様がんは30年間の闘病後に再発するのでしょうか?カルシトニン値が高いということは癌の再発を意味しますか?
甲状腺髄様がんの手術後は、将来再発する可能性があるため、転移の有無を確認します。手術の結果や腫瘍の進...
水頭症の原因には、先天性奇形や後天性感染症などがあります。
水頭症は日常生活でよく見られる病気です。患者がこの病気にかかると、まず頭が徐々に大きくなります。その...
肩関節周囲炎のさまざまな段階における臨床症状の違いは何ですか?
五十肩の臨床症状は時期によって異なります。一般的に、五十肩の臨床症状は、急性期、慢性期、回復期の 3...
夏の始まりに見逃せないヘルシーレシピ
夏が始まってからは、気温も徐々に上昇し、イライラしたり、怒りを感じたりすることも少なくありません。天...
鼻咽頭がんの再発の症状とその治療法
鼻咽頭がんが再発するとどのような症状が現れますか?どのように治療すればいいですか?鼻咽頭がんの再発の...
腎臓がんの診断方法
腎臓がん(腎臓癌)は腎臓に発生する癌性疾患です。腎臓がんの大きさに関わらず、約80%の患者は初期段階...
前立腺炎を改善するための食事療法
冬虫夏草と鴨のシチュー老いた雄のアヒル1羽、冬虫夏草15グラム。鴨の胃の中に冬虫夏草を入れ、適量の水...
大腿骨頭壊死の患者が増えているのはなぜですか?
大腿骨頭壊死の発生率は近年著しく増加傾向にあり、その主な原因は次の 4 つの点です。1. ホルモン ...
進行した肝臓がんの食事をどのように管理すればよいでしょうか?進行性肝がんに対する食事療法の3つの原則
肝臓がんの死亡率は非常に高いです。肝臓がんの患者は病気に苦しめられることになる。進行した肝臓がんの患...
女性の不妊症の予防は、まず体を温めることから始めるべきである
気候がだんだん涼しくなるにつれて、女性は風邪をひかないように特に注意して保温する必要があります。風邪...