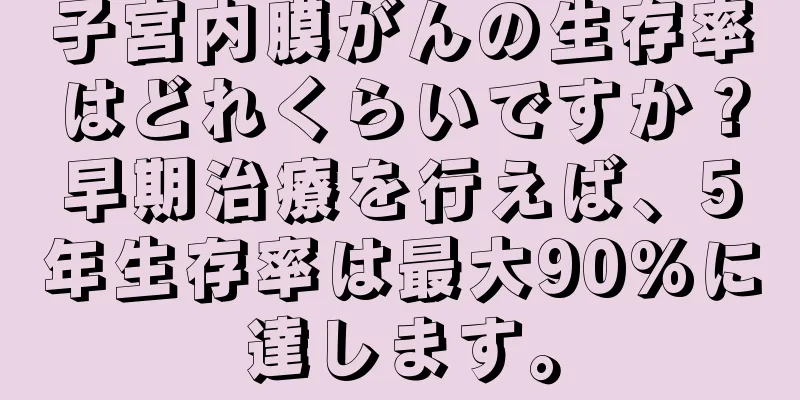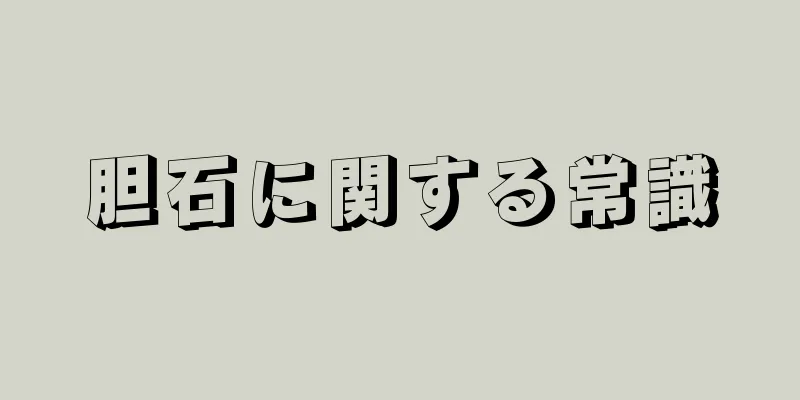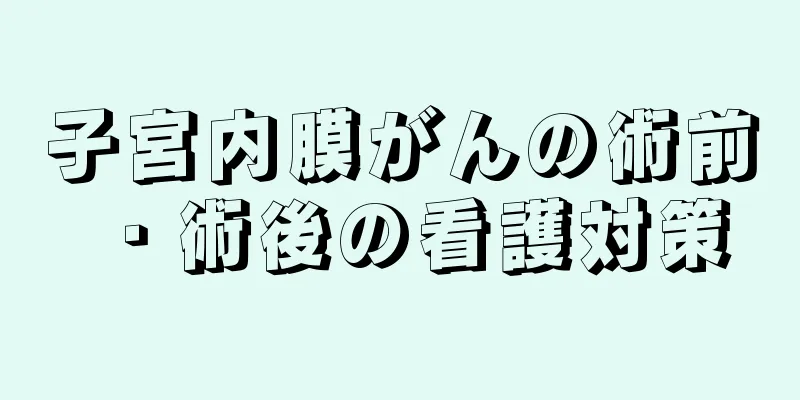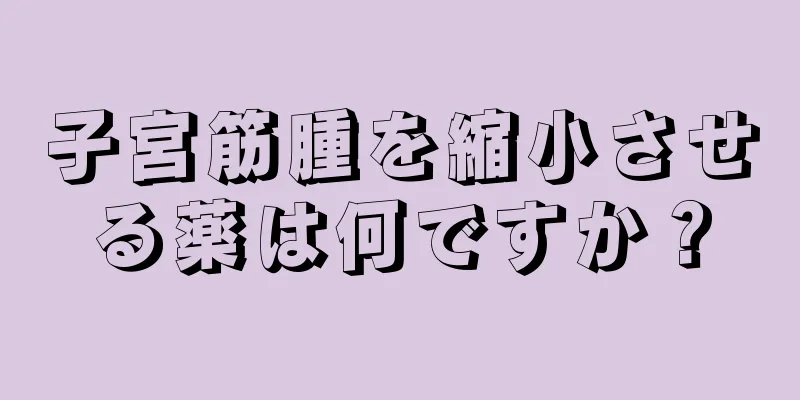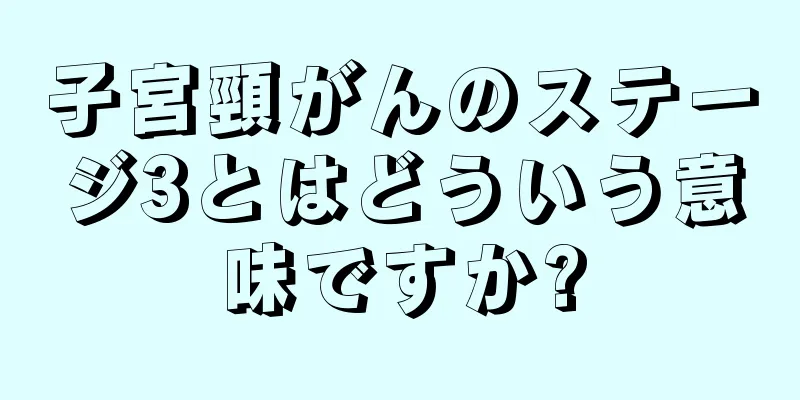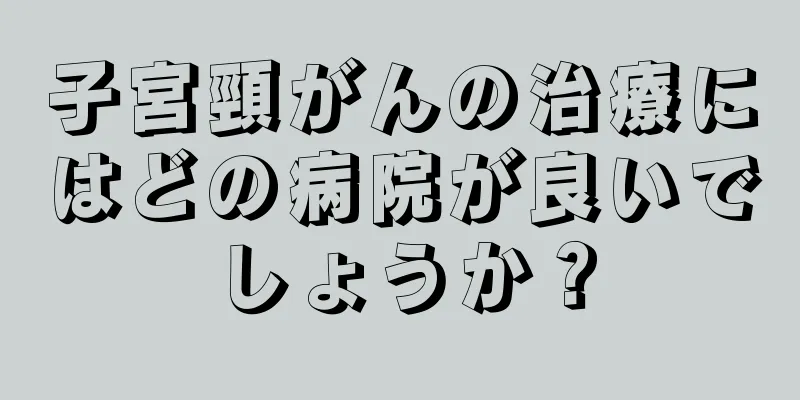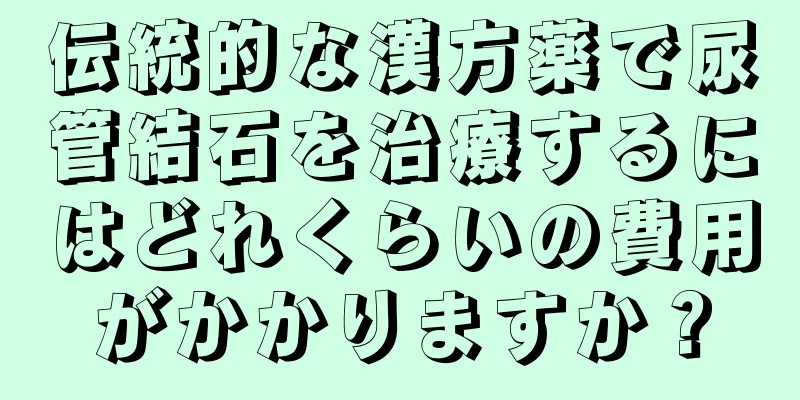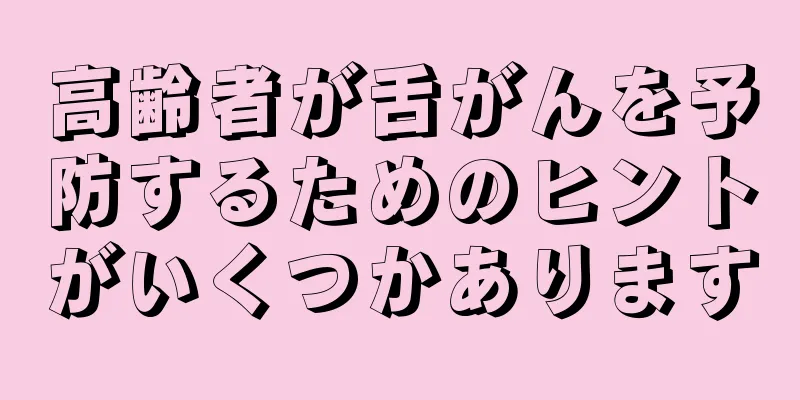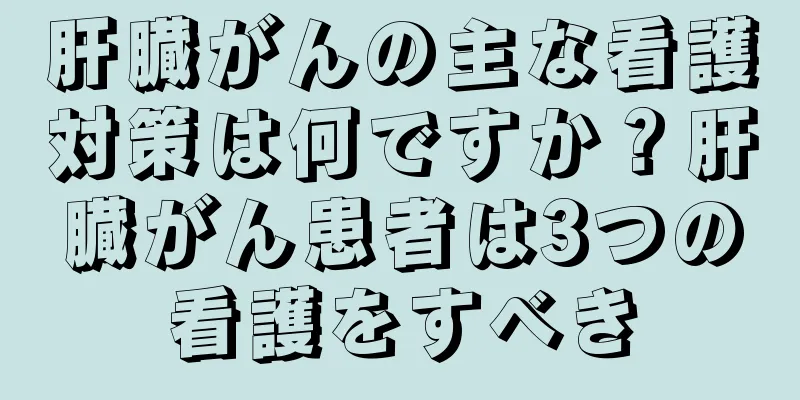乳幼児の漏斗胸の悪化を防ぐ方法
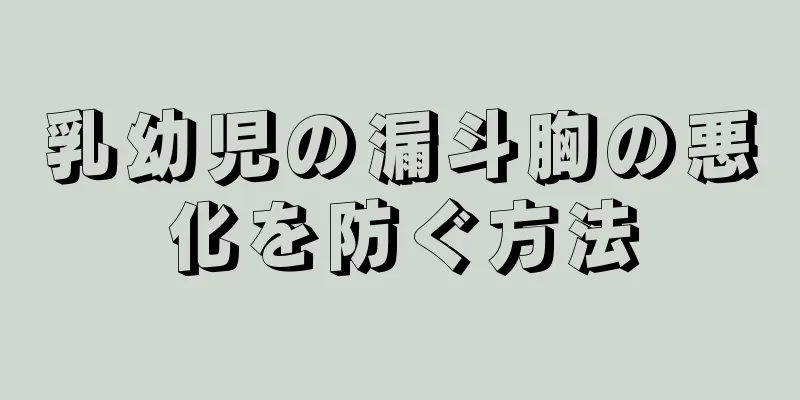
|
王さんは昨年、男児を出産したが、生後7カ月になったばかりの赤ちゃんは地元の母子保健病院で漏斗胸と診断された。地元の医師に相談したところ、漏斗胸は先天性の病気であることが分かりました。しかし、王さんの妻は出産前に母子保健病院で総合検査を受け、胎児に病気は見つからなかった。さらに、王氏とその妻の家族にはこの病気の遺伝歴はない。出産後、漏斗胸の症状は見られませんでした。子どもの胸骨の発育に注意が払われなかったため、検査のために病院に行った数日後に初めて漏斗胸が発見されました。今のところ、私の赤ちゃんは風邪をひいたのは一度だけです。彼の尿は非常に黄色くて濃く、便は少し黒くて量は少ないです。彼は生後7ヶ月ですが、まだ立つことができず、まっすぐに立ったり、安定して座ったりすることができません。家族全員がとても不安でした。漏斗胸を治す薬がないことを知り、彼らはさらに困惑した。漏斗胸の症状が悪化するのを防ぐ方法があるかどうかは分かりませんでした。 医師は王さんの悩みに答えを与えた。遺伝性疾患の家族歴のない生後7か月の子供の場合、その子供の漏斗胸はカルシウム欠乏によって引き起こされたと考えられます。血中カルシウム濃度を適時にチェックするのが最善です。通常の高レベルの病院に行って微量元素の含有量をチェックし、その後、通常の治療コースに従ってカルシウムを補給することで、大きな改善を達成できます。 実際、経口カルシウム補給だけに頼るだけでは不十分な場合があります。必要に応じてビタミンD3の注射が必要になりますが、少量から始めることができます。例えば、1回あたり10万単位(1本あたりビタミンD3 30万単位、1回あたりチューブの3分の1を使用)を投与し、1か月後に状況を観察し、必要に応じて2、3回繰り返します。ビタミンD3を注射する前に、グルコン酸カルシウム、炭酸カルシウムなどのカルシウムを5日間補給する必要があります。最大 2 回で明らかな改善が見られます。今後は、子どもたちの体力強化や胸郭拡張運動の支援に注力していかなければなりません。 |
<<: 妊婦へのカルシウムとビタミンDの補給は胎児漏斗胸を予防できる
推薦する
腰椎椎間板ヘルニアの原因
腰椎椎間板ヘルニアは整形外科ではよく見られる病気です。現在、発症メカニズムには機械的圧迫メカニズム、...
夏の妊娠準備にぜひこのヒントをご活用ください!
初夏がもう到来しました。夏に妊娠の準備をすれば、来年の春から夏にかけて健康で賢い赤ちゃんを産むことが...
O字脚を防ぐためのちょっとした行動
O字型の脚の出現は多くの人々に悩みをもたらしました。ほとんどの人は、O 字脚を予防する方法を知りたい...
3つの効果的な黒色腫治療法
悪性黒色腫には臨床的に有効な治療法が 3 つあり、悪性黒色腫患者が病気の悪化を適時に抑制し、悪性黒色...
胆嚢ポリープの治療で評判の良い病院はどこですか?
胆嚢ポリープの治療で評判の良い病院はどこですか?これは多くの患者が抱く疑問です。ご存知のとおり、胆嚢...
多嚢胞性卵巣症候群の患者は糖尿病を患っている可能性がある
多嚢胞性卵巣症候群は、妊娠可能年齢の女性に起こる複雑な内分泌異常と代謝異常によって引き起こされる一般...
風邪や咳をひいている妊婦はビワジュースを飲んでも大丈夫ですか?
風邪や咳をひいている妊婦はビワジュースを飲んでも大丈夫ですか?食べられますよ。妊婦は、その特殊な身体...
3つの一般的な外痔核の特定の症状の分析
痔は発生する場所によって外痔核と内痔核に分けられ、それぞれ痔の症状も異なります。比較的、外痔核の症状...
子宮がんはどのように診断されますか?
どのような種類の癌でも、初期症状は特に明らかではないため、患者に多くの問題をもたらし、適切なタイミン...
肛囲膿瘍と痔の違いは何ですか?
肛門周囲膿瘍と痔は、2 つの一般的な肛門直腸疾患ですが、原因、症状、治療法は異なります。肛門周囲膿瘍...
専門家が血管腫が人体に及ぼす害を解説
血管腫は非常に危険な病気ですが、ほとんどの人はそのことをあまり知らないと思います。では、血管腫の危険...
腰椎椎間板ヘルニアの治療法
腰椎椎間板ヘルニアの治療法:腰椎椎間板ヘルニアの治療法としては、一般的に安静、外用薬、経口薬、牽引療...
くる病を予防する効果的な方法
くる病は人生において非常に一般的であり、特に子供ではカルシウム欠乏によりくる病を発症する可能性が最も...
肺がんの早期診断方法
肺がんが早期に診断された場合は外科的治療が必要となり、術後の病理検査で再診断が行われます。肺がんCT...
低温やけどの症状は何ですか?
冬は低温やけどが起こりやすい季節です。冬に入り、気温が下がると、暖房の需要も増える人が多くなります。...