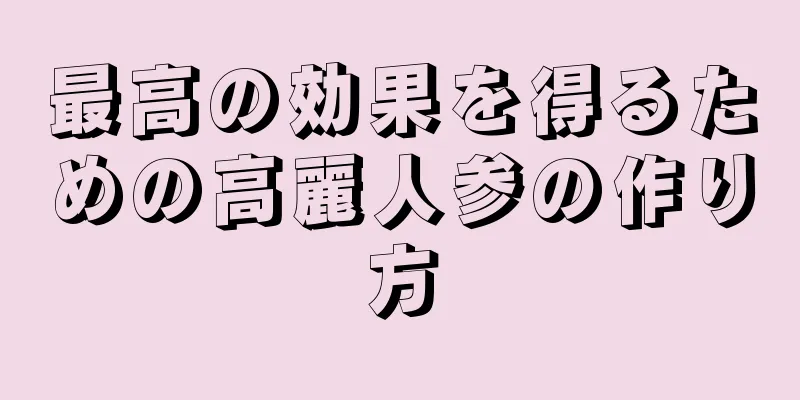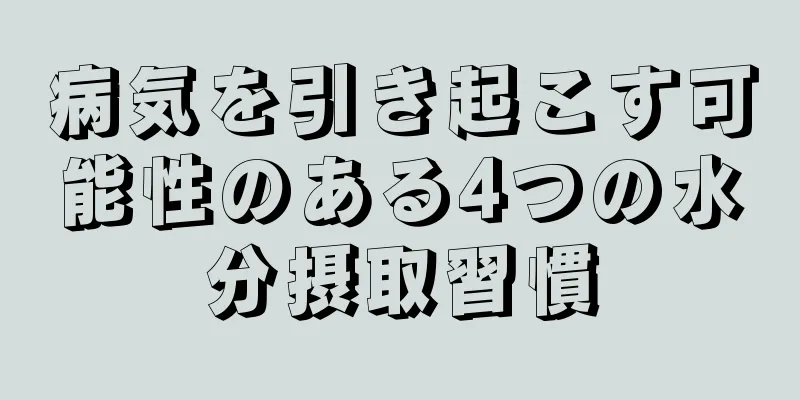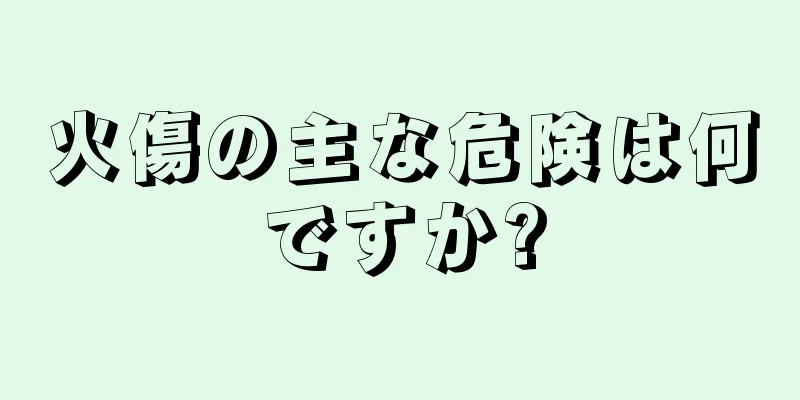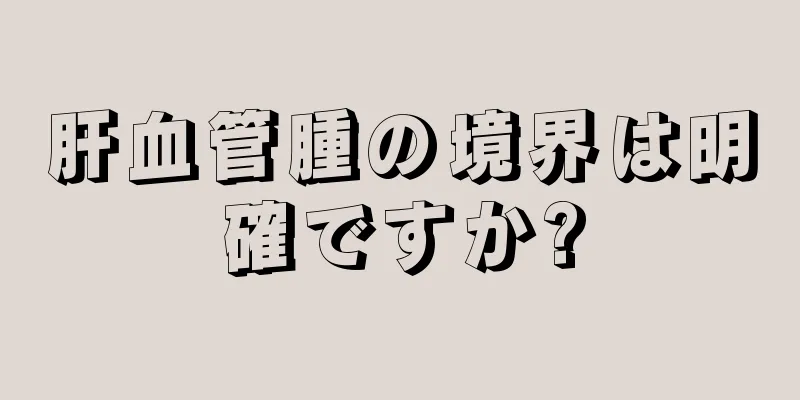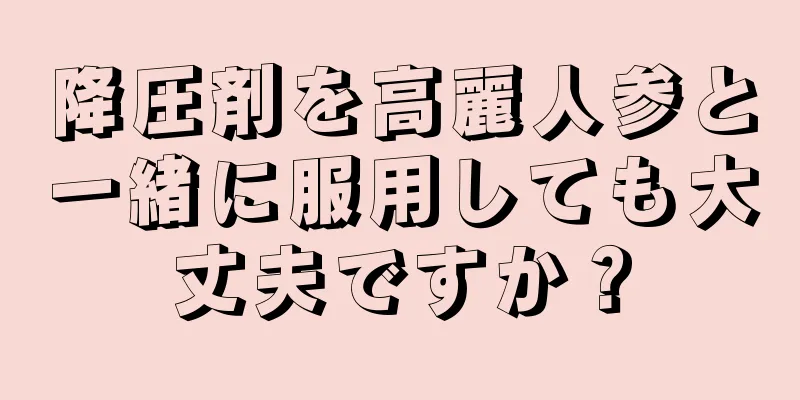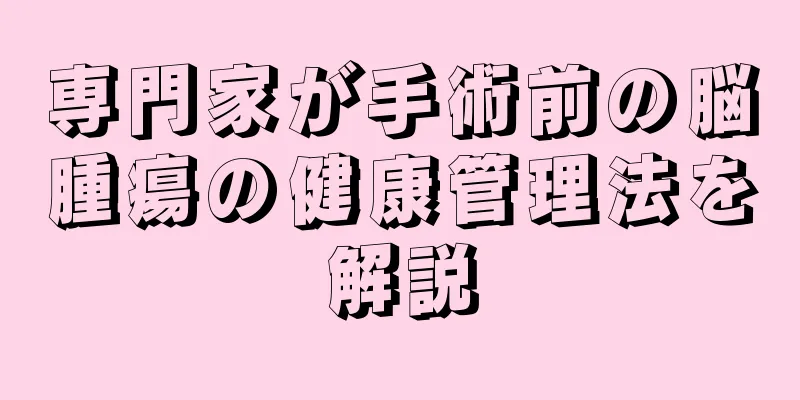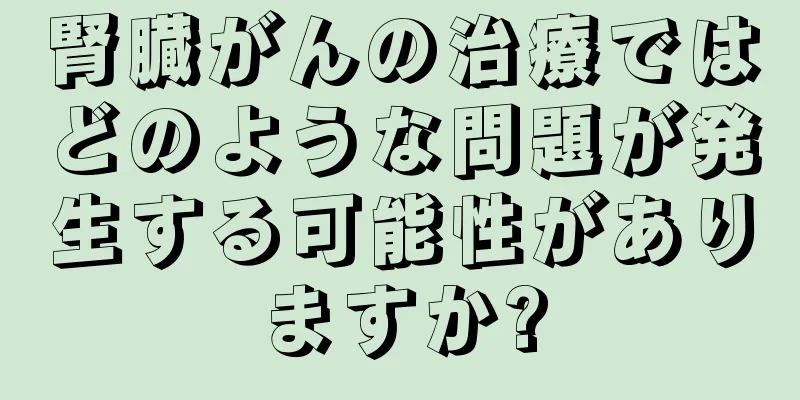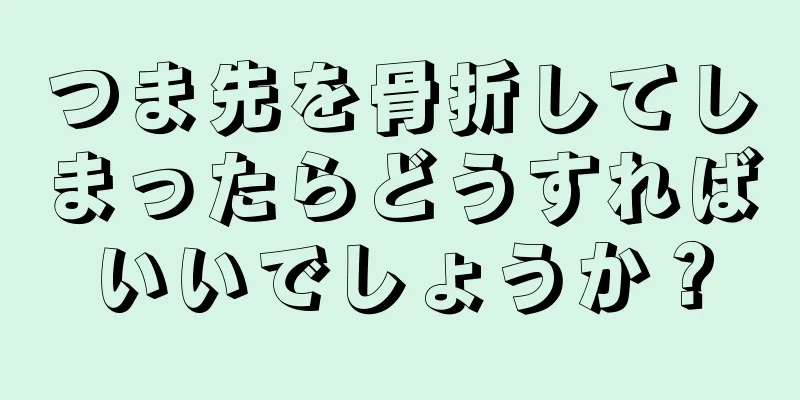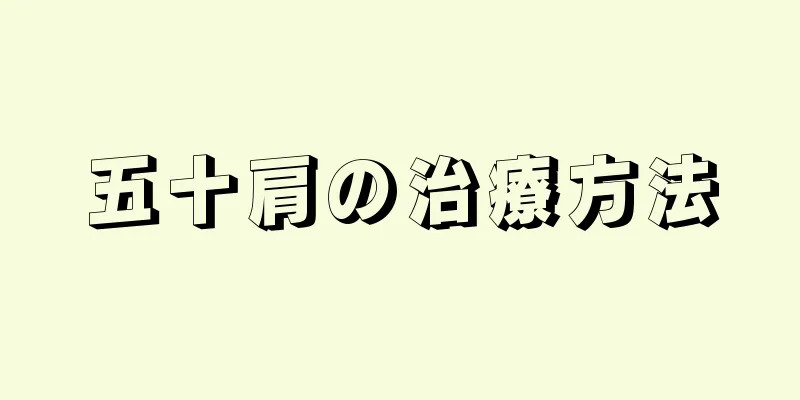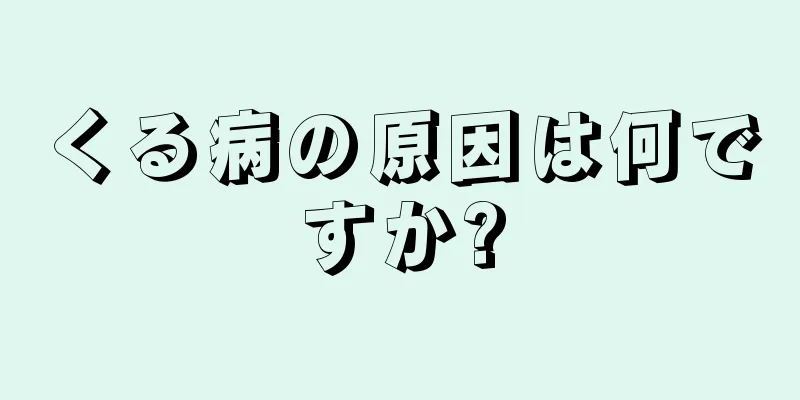化膿性掌側腱鞘炎の治療
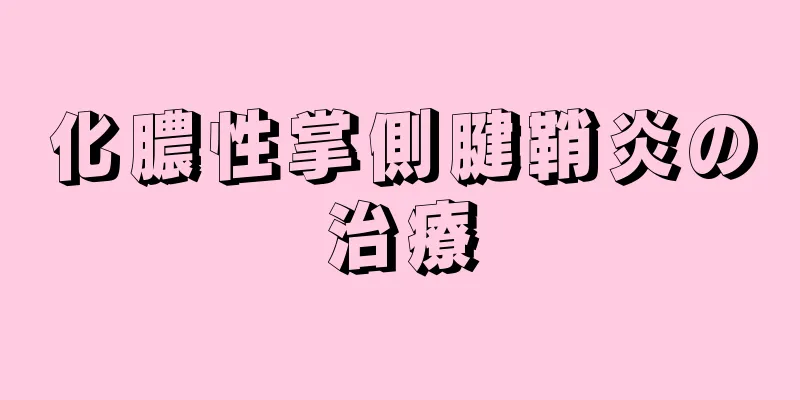
|
掌側化膿性腱鞘炎は、黄色ブドウ球菌によって引き起こされる手のひらの深部の化膿性感染症です。感染と化膿の後、炎症は広がりにくくなり、深部組織に広がり続け、滑液包と掌側腔の感染を引き起こします。 全身治療 経口コトリモキサゾールや注射用ペニシリンなどの早期全身抗生物質が使用されます。障害のある指は機能的位置で平らに固定され、ブレーキをかけながら休められます。重度の全身反応がある患者には、銀桔末や黄連結湯などの漢方薬を併用して治療することが推奨されます。 局所治療 初期段階では、紫外線、超短波、赤外線などの物理療法、または如意金黄粉末とイクチオールの外用を行う必要があります。積極的な治療を行った後も痛みがひどい場合は、腱の圧迫壊死を防ぐために早期に切開と除圧を行う必要があります。 化膿性腱鞘炎: 中指関節と近位指関節の側面を縦に切開します。腱の損傷を避けるため、手のひらの正中線を切開しないでください。皮下組織を分離する際には、腱鞘を明瞭に識別し、神経や血管を傷つけないようにする必要があります。排液のためにラテックスシートを切開部に挿入する必要があります。 化膿性滑液包炎:親指の中間節の側面と母指球の掌側表面に約 1 cm の切開を加えます。皮下組織を剥離した後、細いプラスチックチューブを挿入し、排液を行います。尺骨滑液包炎が小指の腱鞘炎を伴う場合は、小指球の掌側表面と小指の外側面を切開します。 深掌側腔感染症:母指球感染症の切開は、手のひら表面の腫れや波打つ部分、通常は母指屈筋と掌側腱膜の間で行われます。近くの小さな動脈を傷つけないように、「虎の口」の裏側には刺してはいけません。中掌間隙感染症の切開は、浅掌側動脈弓の損傷を防ぐために、手のひらの横線を超えないように、中指と薬指の指間部分の手のひら表面に施されます。切開後、排液のためにラテックスシートを挿入します。 |
推薦する
手首を骨折した後、指が曲がらなくなるのはなぜですか?
手首を骨折した後、指が曲がらなくなるのはなぜですか?手首の骨折後に指が硬くなる原因は、身体が完全...
女性の不妊症を防ぐには、喫煙をやめ、アルコール摂取を控える
喫煙と飲酒のライフスタイルは、特に子供を産みたいカップルにとって、極めて不健康です。一方または両方が...
直腸がんの原因は何ですか?
直腸がんは人体によく見られる悪性腫瘍の一つです。この病気の原因は今のところまだよくわかっていません。...
腰椎椎間板ヘルニアの患者は、その診断を正しく理解する必要がある。
腰椎椎間板ヘルニアは誰もがよく知っている一般的な病気です。中高年によく見られます。腰椎椎間板ヘルニア...
大腸がんの手術から1年後の食生活で注意すべきことは何ですか?
胆嚢がんの食事療法の原則には、ビタミンが豊富な食品を多く食べることも含まれます。ビタミン C とビタ...
末期膵臓がんのケア方法
膵臓がんは現在、世界で最も一般的ながんの一つです。一般の患者さんの家族や患者さんにとって、治療やケア...
喫煙は前立腺がん手術後の生化学的再発リスクを高める
喫煙は多くの腫瘍の危険因子ですが、前立腺がん(PCa)に関しては議論があるようです。いくつかの研究で...
前立腺がんにニンニクとタマネギを食べる
研究によると、ニンニクとタマネギは私たちの日常生活でよく使われる野菜ですが、口の中になかなか取れない...
尿路感染症は月経中の女性に多くみられる
尿路感染症に苦しむ主なグループは女性です。女性が尿路感染症にかかりやすい理由は、確かに身体的な違いに...
胸膜炎患者の看護のポイントは何ですか?
胸膜炎の患者さんのケアの重要なポイントは何ですか?多くの人が胸膜炎に苦しんでいます。胸膜炎の定期的な...
専門家が明かす:静脈瘤を防ぐ10の習慣
生活の中でどのような習慣が静脈瘤の発生を防ぐことができますか?静脈瘤を予防するにはどうすればいいでし...
脳血管けいれんによるめまいが起こった場合の対処法
最近、めまいに悩む人が増えていますが、そのかなりの割合は脳血管けいれんが原因です。この病気は致命的で...
女性にとって海藻を食べることの利点
今日は、女性が海藻を食べることで得られるメリットについてまとめてみました。見ていきましょう。毎日海藻...
揚げ塩温湿布で首を温め、頸椎症の症状を緩和する
頸椎症の患者は、主に首や肩の痛み、上肢の筋力低下、指のしびれ、めまい、頭痛、筋萎縮などの症状を経験し...
胃がんの胃切除後の平均余命はどれくらいですか?これらの要因に関連して
胃がんの胃切除術を受けた患者が20歳未満であれば、通常は3年以上生存することができます。 21歳から...