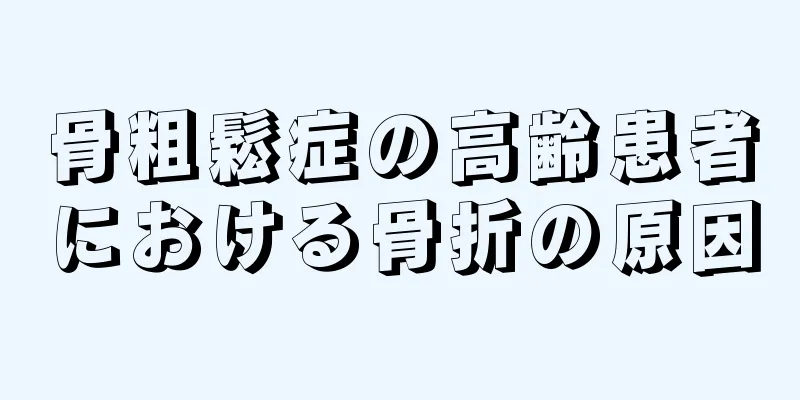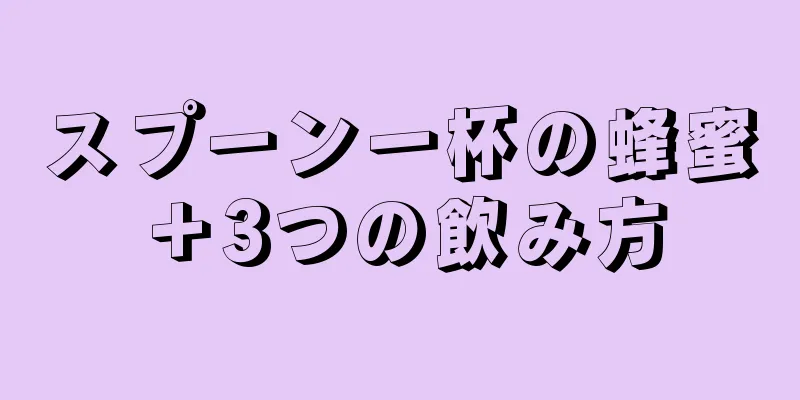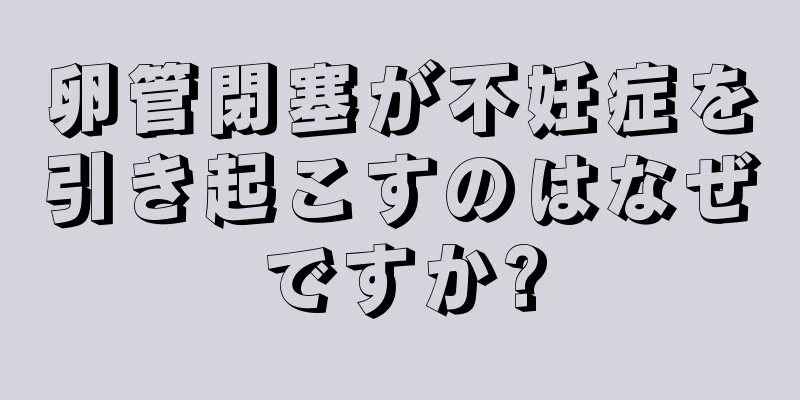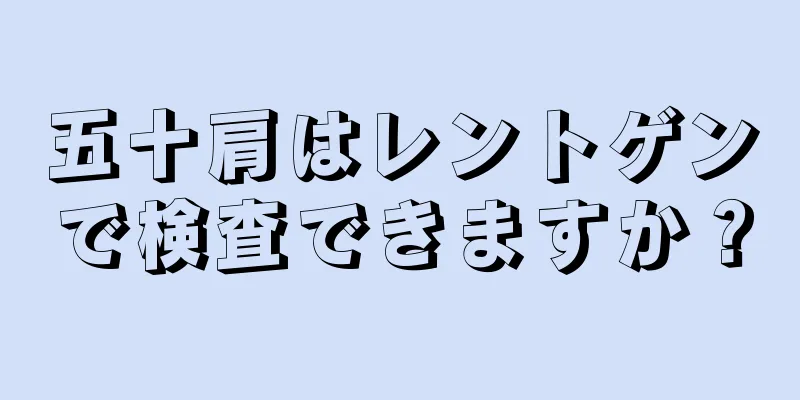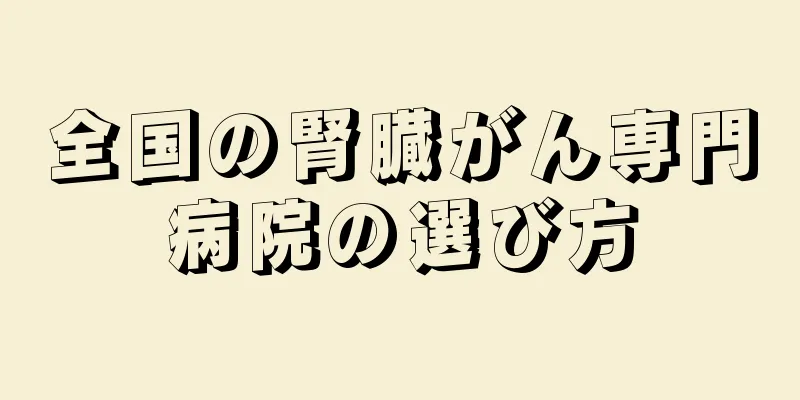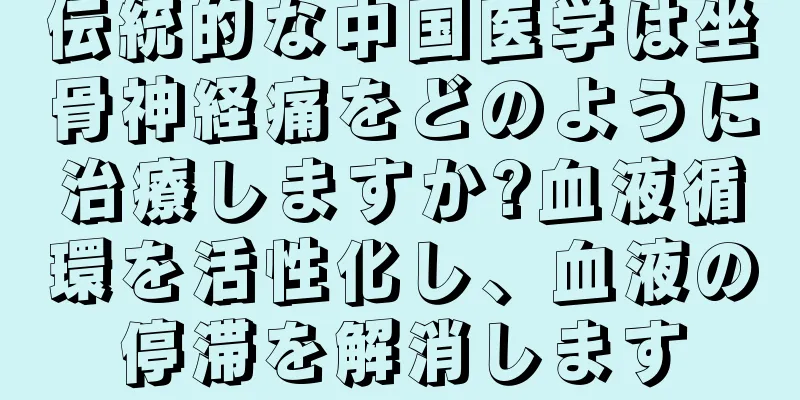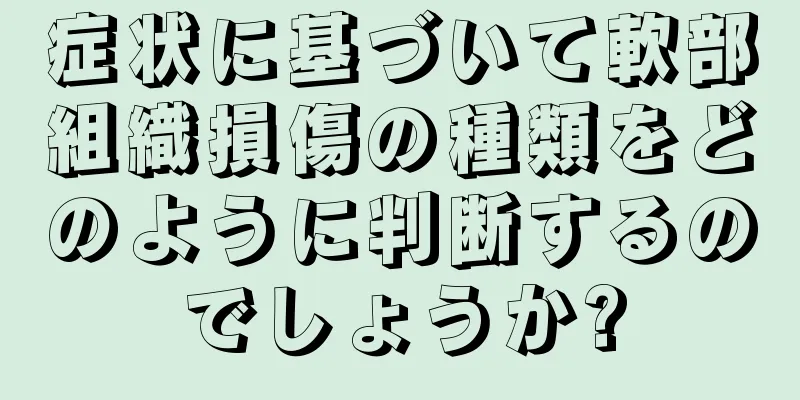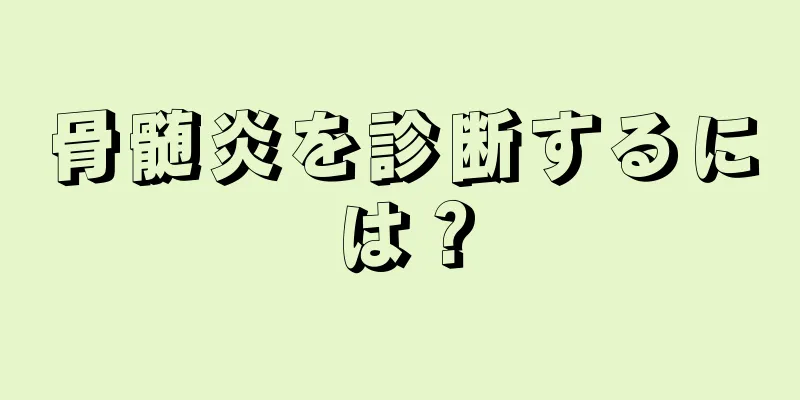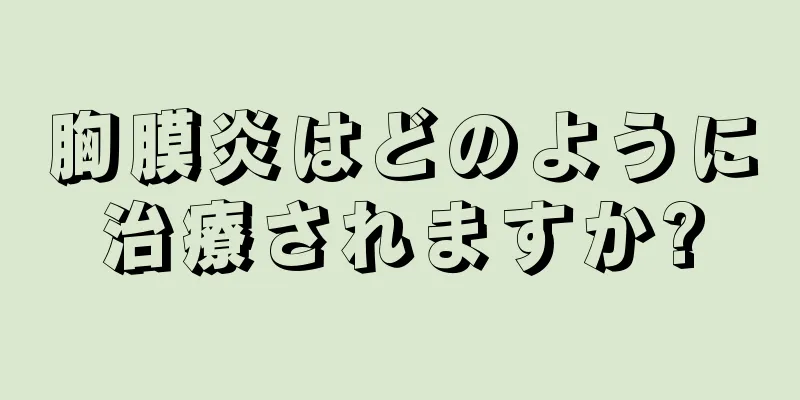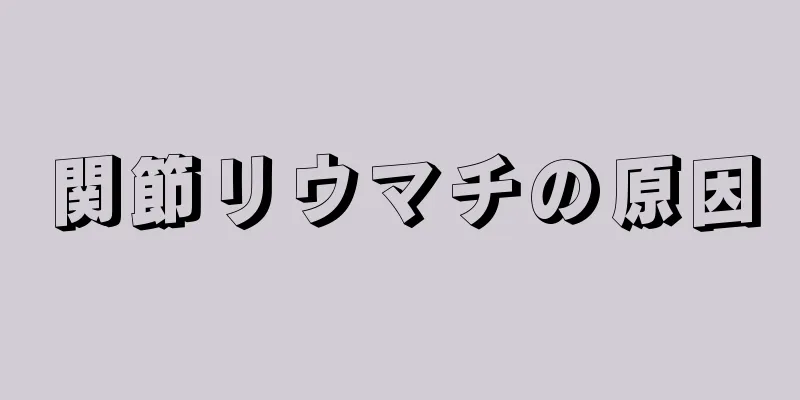乳房嚢胞を予防する5つの方法
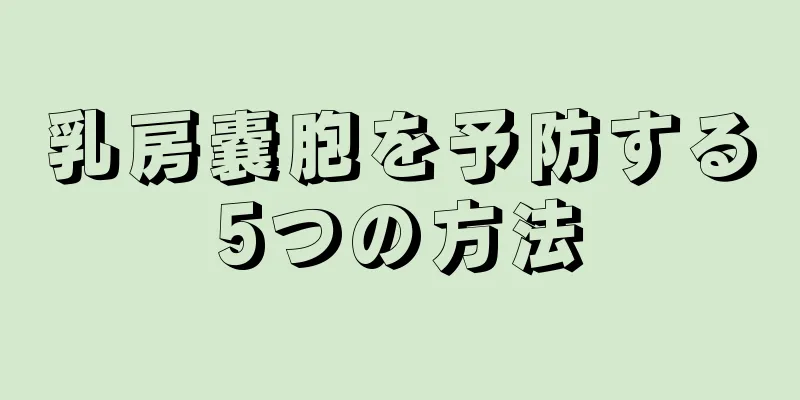
|
乳房嚢胞が蔓延している今日の世界では、多くの人がその病状に対する理解不足やその他の理由により治療を遅らせ、深刻な結果をもたらしています。早期発見・早期治療が難しいため、乳房嚢胞の予防が特に重要です。積極的な予防のみが、この病気によって引き起こされる害をより良く、そして徹底的に回避することができます。乳房嚢胞を予防する5つの方法をご紹介します。 1. 心理的予防。過度の緊張、心配、悲しみなどの悪い心理的原因は、身体の衰弱、内分泌障害を引き起こし、乳房嚢胞などの乳房疾患を誘発する可能性があります。したがって、乳房嚢胞を避けるためには、怒りを抑え、安定した気分を保つことに注意する必要があります。 2. 仕事と休息を組み合わせ、過度の疲労を避け、適切な身体活動に参加します。活動はあらゆる病気を予防する最良の方法です。活動を増やすことで体の免疫力が高まり、乳房嚢胞の発生を減らすことができるからです。 3. 乳房嚢胞の患者は食生活を変え、油分の多い食べ物を控え、肥満を防ぎ、エストロゲンを含む薬の使用を避け、エストロゲンを含む避妊薬や美容製品の乱用を禁止し、エストロゲンを与えられた鶏肉や牛肉を食べないようにする必要があります。これらは乳房嚢胞を引き起こしたり、乳房嚢胞を悪化させる可能性があるからです。 4. 夫婦間の調和のとれた性生活を維持するために、日常生活は仕事と休息を組み合わせた規則正しいものであるべきです。これにより、内分泌を効果的に調節し、乳がんの可能性を減らし、乳房嚢胞を予防することができます。 5. 適切なセレンサプリメントを摂取する。セレンは人体に欠かせない微量元素であり、強力な抗酸化能力を持っています。セレンの補給は細胞の抗酸化能力を高め、内分泌と代謝を調節し、体内の毒素を除去することができ、乳房疾患の予防に非常に効果的です。しかし、セレンを摂りすぎると 上記の 5 つの方法は、理解すれば誰にとっても役立つものになると信じています。皆様にご理解いただき、ご注目いただければ幸いです。 |
推薦する
骨折の初期症状は何ですか?
骨折の初期症状は何ですか?骨や軟骨の完全性や連続性を破壊する傷害を骨折といいます。では骨折しているか...
神経膠腫の治療法は何ですか?
神経膠腫は、神経膠腫、または略してグリオーマとも呼ばれ、神経外胚葉に発生する腫瘍です。これは私たちの...
卵巣がんの治療に使われる西洋医学は何ですか?
卵巣がんは死亡率の高い悪性腫瘍であり、女性の生命と健康を深刻に脅かす重大な病気です。卵巣がんは最初に...
緩和手術は直腸がんの治療に役立つ
直腸がんは不健康な生活習慣によって引き起こされる病気です。直腸がんを治療する方法はたくさんあります。...
乳房結節によく使われる薬は何ですか?
一般的に、病気が発生した場合、薬物治療は多くの時間を費やすことがなく、仕事や勉強に影響を与えないため...
腎臓がんの原因に注意を払う必要がある
腎臓がんの発生は私たちの日常生活に大きな影響を与えますが、腎臓がんの原因に十分な注意を払っていない人...
反射の変化は腰椎椎間板ヘルニアの典型的な兆候である
腰痛や脚の痛みは、主に腰椎の湾曲の変化によって起こる腰椎椎間板ヘルニアの一般的な症状です。では、腰椎...
肛門裂傷は寿命に影響しますか?
裂肛が患者さんの人生や身体に大きな影響を与えることは、皆さんもご存知だと思います。裂肛は肛門直腸疾患...
春に欠かせない健康維持のための薬膳食品5選
1. 百合もち米粥ユリ90グラム、もち米300グラム、適量の黒砂糖を水に加えて粥状にし、1日1回、7...
血管炎の再発を防ぐ方法
血管炎は血管の損傷に関連する病気です。また、全身のさまざまな臓器にさまざまな程度の損傷を引き起こす可...
頸椎症の発症を効果的に予防するにはどうすればいいでしょうか?
生活のプレッシャーが増すにつれ、頸椎症に苦しむ人が増えています。頸椎症の予防方法を理解することは、頸...
専門家が関節炎治療の外科的治療法を解説
臨床的には、手術は関節炎治療の主な方法であり、関節炎治療に優れた効果があるため、患者から非常に求めら...
頸椎症の病態生理はどのように変化するのでしょうか?
頸椎症の病態生理学的変化は以下のとおりです。 (1)頸椎椎間板は血液供給のない組織である。軟骨終板の...
頸椎症の治療に関する誤解に注意を払わない人もいる
頸椎症の治療に関する誤解に注意を払わない人が時々いますが、それがさまざまな結果につながります。では、...
心房中隔欠損症の検査にはどのようなものがありますか?
現在、心房中隔欠損症に苦しむ人が増えており、特に新生児の多くがこの病気にかかりやすい傾向にあります。...