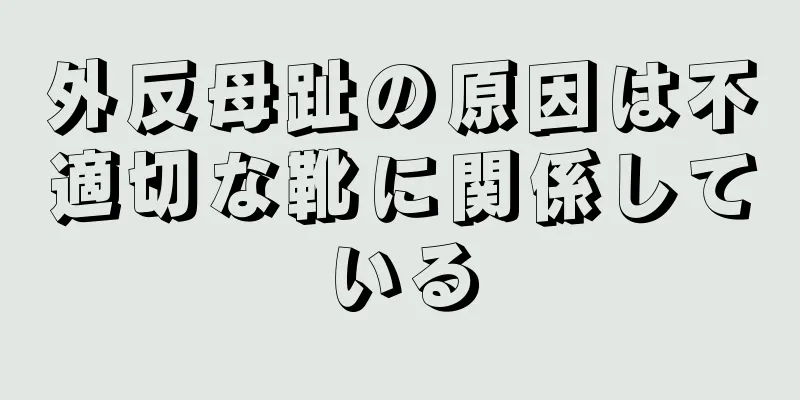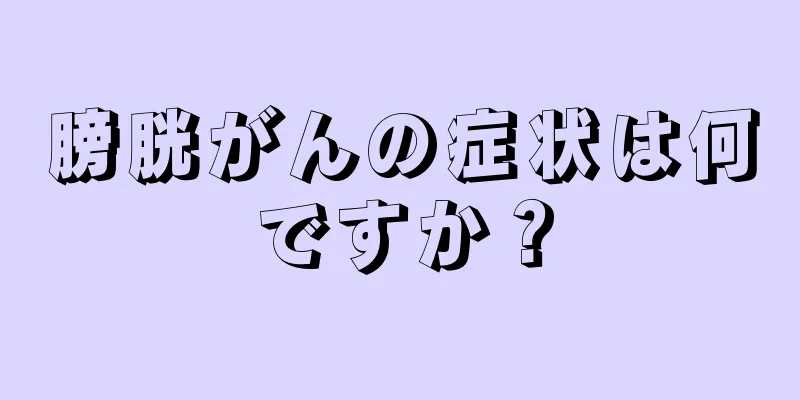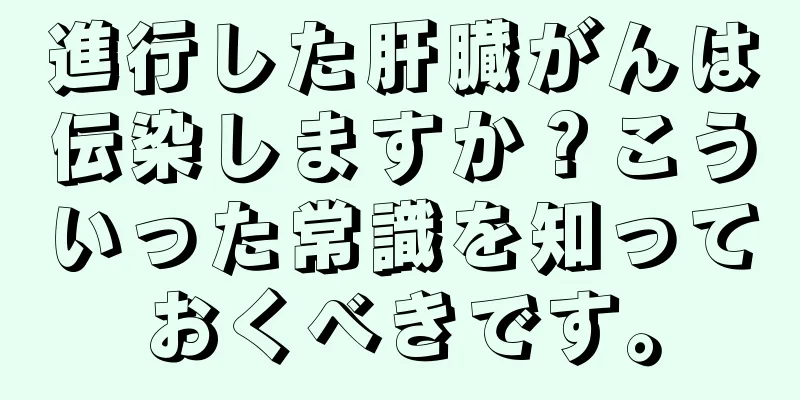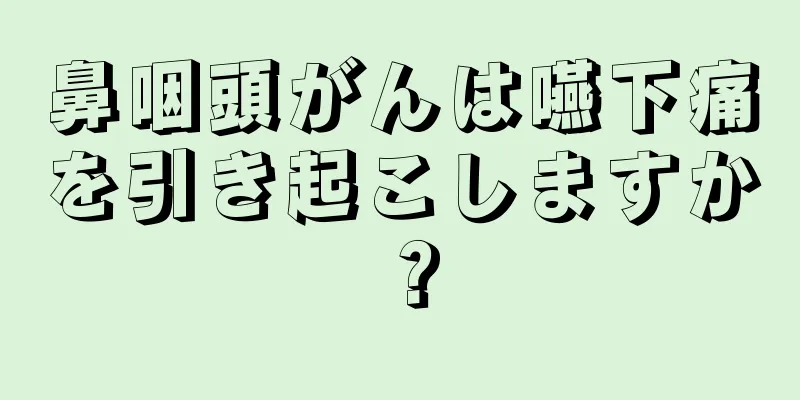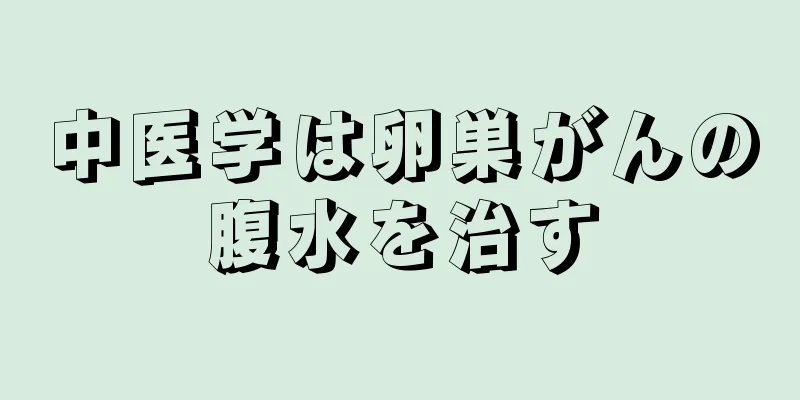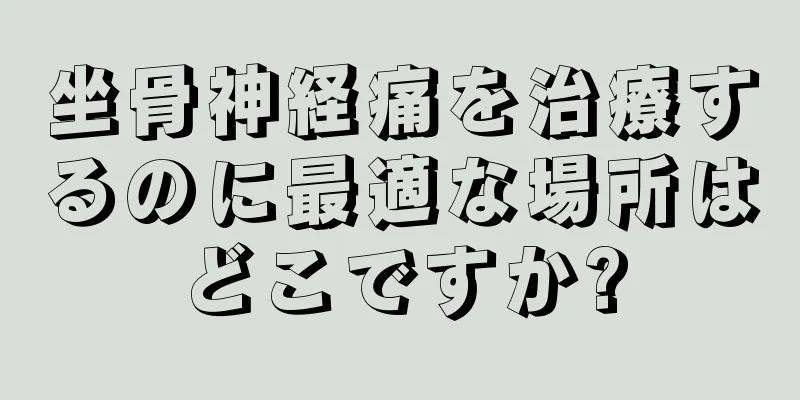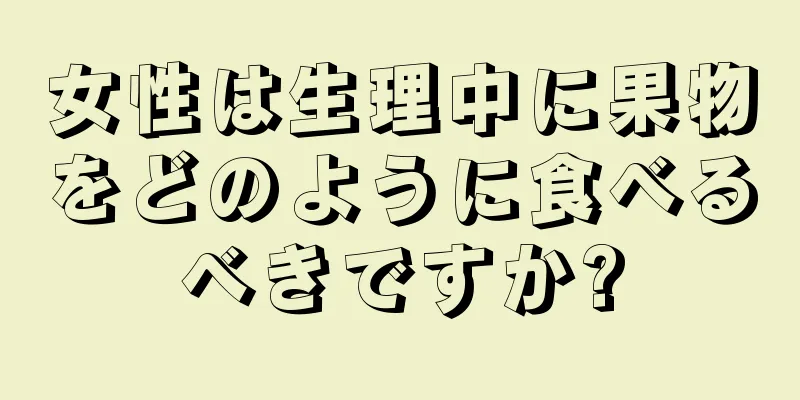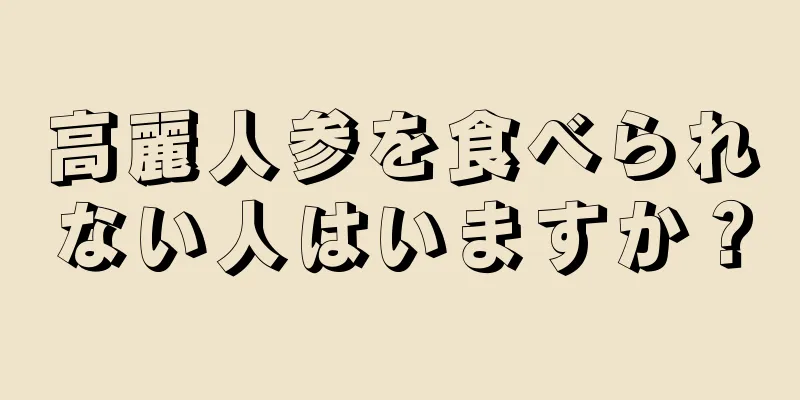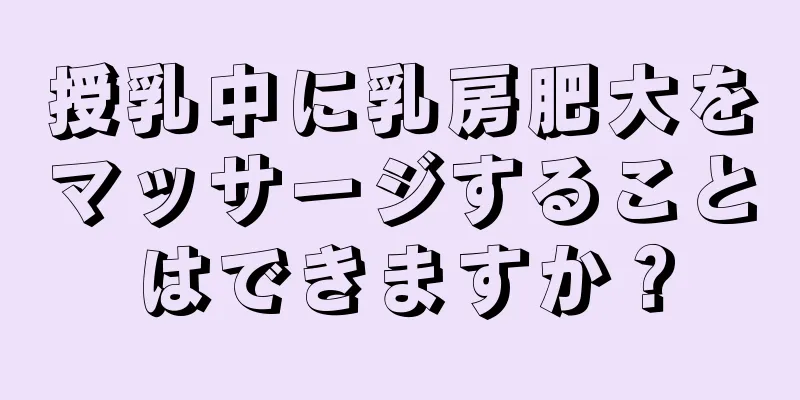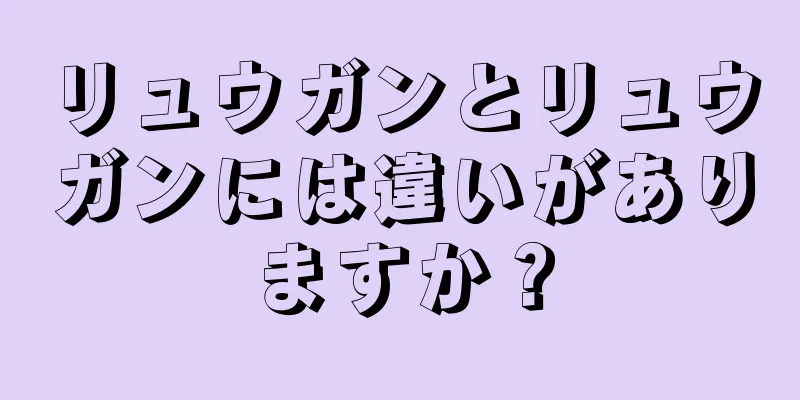カルシトニンは骨粗鬆症による骨の痛みの治療に使用できますか?
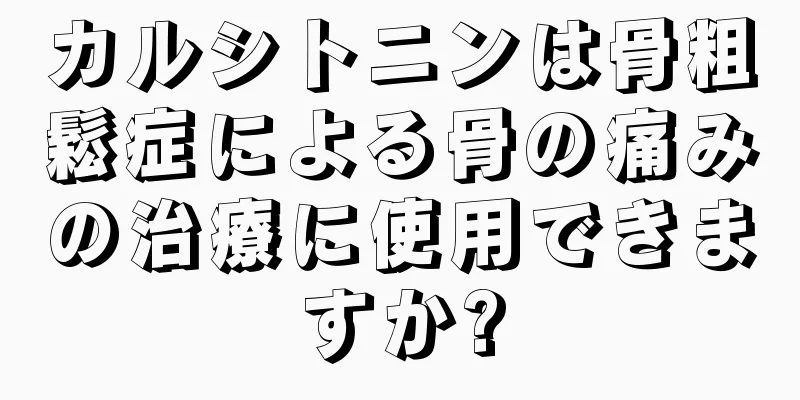
|
骨粗鬆症は体の多くの部分に痛みを引き起こしますが、最も一般的な痛みは腰痛で、痛みを抱える患者の 70%~80% を占めています。痛みは背骨に沿って両側に広がります。痛みは仰向けや座位では軽減しますが、直立したり背筋を伸ばしたり、長時間立ったり座ったりすると痛みが悪化します。また、患者が骨折しやすくなる可能性もあります。骨折は、変形性骨粗鬆症の最も一般的かつ最も深刻な合併症です。また、呼吸機能の低下、胸椎後弯、胸郭変形、肺活量および最大換気量の減少を引き起こすこともあります。患者は胸の圧迫感、息切れ、呼吸困難などの症状を経験することがよくあります。カルシトニンを摂取できますか? カルシトニンは骨粗鬆症による骨の痛みの治療に使用できますか? 1 カルシトニンは近位尿細管によるカルシウムとリンの再吸収を阻害し、尿中へのカルシウムとリンの排泄を増加させ、血中カルシウムとリンを減少させます。痛みを和らげる効果もあり、骨粗しょう症の痛みを和らげる効果もありますが、その作用機序は医学的にはあまり明らかではありません。中枢神経系を通じて直接作用する可能性があります。 2 骨粗鬆症の治療の目的は、痛みを和らげることではなく、その原因を治療することです。カルシトニンは中等度以上の痛みに使用できます。カルシトニンを服用すると一時的に痛みを和らげることができますが、時間が経つと効果がなくなるため、長期間服用するのは患者には適していません。 3 骨粗しょう症の患者は、豆類や豆製品、グルテン、米、ピーナッツなど、カルシウムを多く含む食品をより多く食べることができます。肉、卵、牛乳の選択肢:牛乳、魚、エビやカニ、卵、赤身の肉、干しエビなど。野菜の選択肢:ニンジン、ピーマン、トマト、セロリなど。 予防 患者は体の痛みを軽減するために、身体運動にもっと注意を払う必要があります。塩辛い食べ物や辛い食べ物はカルシウムの損失を促進し、症状を悪化させるので避けるべきです。早く回復することを祈っています。 |
推薦する
初期の良性胃腫瘍の症状は何ですか?
良性の胃腫瘍はまれな病気です。良性胃腫瘍の症状は早期発見・早期治療すれば治ります。では、良性の胃腫瘍...
大腸がんの早期診断方法
一般的な腸の病気である直腸がんの場合、病気の初期段階では症状があまり明らかでなく、患者は胃腸炎などと...
膀胱炎の病院での検査と治療の費用
膀胱炎は人生においてよくある病気であり、治療は容易ではありません。そのため、膀胱炎を患った後の治療費...
五十肩の予防法は何ですか?
最近、友人の中にも肩関節周囲炎に悩まされている人がいるという話をよく聞きます。この病気は私たち人類に...
日常生活で腰椎椎間板ヘルニアを予防する方法
腰椎椎間板ヘルニアは頻繁に発生します。実は、腰椎椎間板ヘルニアの予防について知らない人が多く、腰椎椎...
骨折の原因は何ですか?
骨折は私たちの生活の中で頻繁に起こります。多くの場合、激しい運動中の衝撃によって引き起こされます。多...
悪性リンパ腫の患者は妊娠できますか?
悪性リンパ腫の患者は妊娠できますか?妊娠しないのが一番です。妊娠するとお腹の中の胎児に必ず悪い影響が...
腸閉塞の治療ではどのような点を考慮すべきでしょうか?
どのような病気であっても、患者さんが早く回復することを望むなら、生活における看護の仕事は不可欠であり...
多嚢胞性卵巣症候群が再発した場合の対処法
最近、多くの人がインターネットで多嚢胞性卵巣症候群の治療法について相談しています。実際、多嚢胞性卵巣...
大腸がん患者はどのような症状を継続的に発症するのでしょうか?
多くの患者は大腸がんの症状を診断できず、大腸がんに対する理解も十分ではありません。多くの人が、大腸が...
鼻咽頭がんの検査は何をすべきか
病気が発見された後、医師は患者の具体的な状態を判断するために総合的な検査を行うように依頼することがよ...
頸椎症の合併症は何ですか?
頸椎症の患者の多くは、不適切な治療や治療の遅れにより、頸椎症の合併症を発症します。では、頸椎症の合併...
火傷についてどれくらい知っていますか?
ご存知のとおり、火傷は私たちの生活の中でよく起こる出来事です。火傷は患者に身体的および精神的な苦痛を...
腰椎椎間板ヘルニアになりやすい人を見つける場所
腰椎椎間板ヘルニアを患っているにもかかわらず、そのことに気づいていない患者さんはたくさんいます。検査...
骨折後の回復を早めるには何を食べたらいいでしょうか?
骨折後の回復を早めるために何を食べるべきかについては、通常、明確な規定はありません。患者は通常、体に...